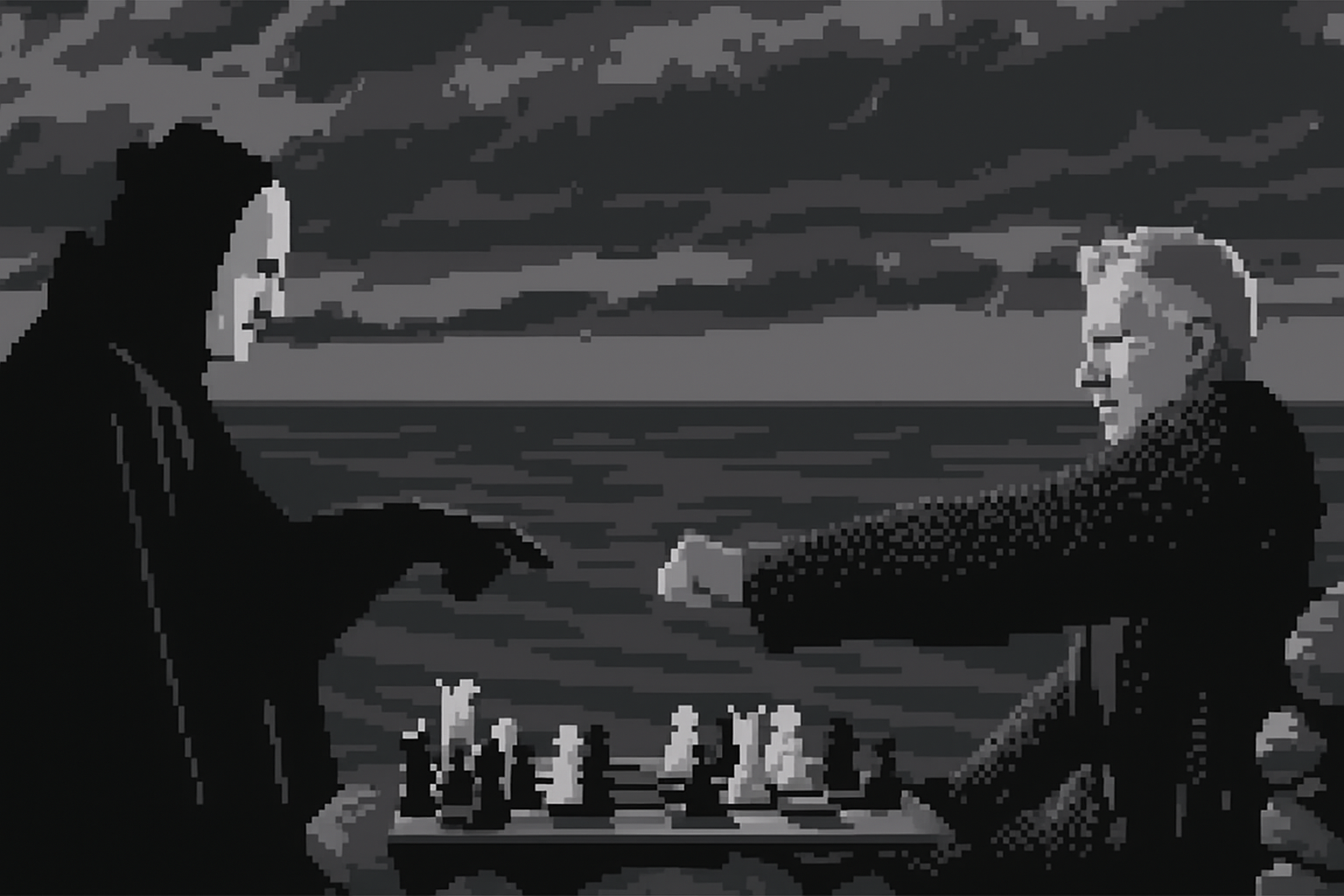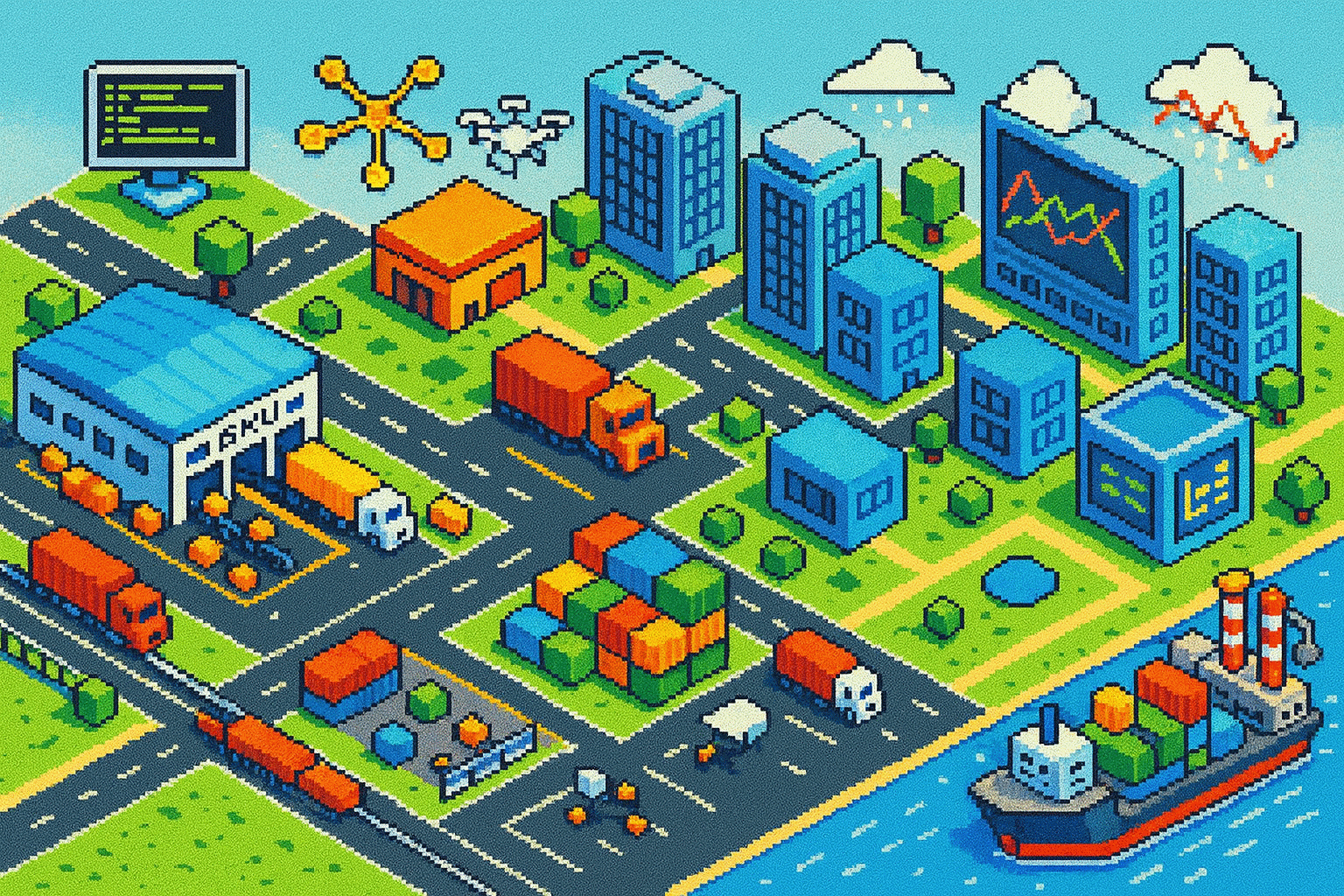供給と需要の整合性の再考
アライメントという言葉は素晴らしい響きを持ちます。しかし、サプライチェーンにおいては、しばしば人々をスプレッドシートに合わせることを意味し、顧客が価値を認めるものに希少資源を合わせることを意味していません。従来の方法は次のようになります: ひとつの予測を選び、営業、オペレーション、財務を集めてその予測に合意し、その後、各種KPIを用いて遵守状況を監視します。この儀式的な手順は安心感を与えますが、経済的には必ずしもそうではありません。

Introduction to Supply Chainでは、私は別の指針を提案しています。サプライチェーンの目的は、数値の周囲の調和を維持することではなく、期待されるリスク調整後のリターンが最も高い場所に資本、能力、そして注意を配分することにあります。本書全体――特に Economics および The Future の章――で、この視点が重要なものを簡潔にし、そうでないものを排除する方法を示そうとしています。
合意形成による整合の問題
企業が「一つの数字のセット」を求めるとき、暗黙の前提として、不確実性が一つの未来に平坦化されるとみなしています。しかし、実際にはそうではありません。市場は不規則で、リードタイムは変動し、需要の裾は無視されると最も大きな打撃を与えるため、重要なのです。コンセンサスの数字はこの変動性を除去するのではなく、単に隠すに過ぎません。
さらに悪いことに、合意形成による整合は、需要を自然の法則であるかのように扱います。価格、品揃え、在庫状況は計画プロセスにおける外生的要素とみなされがちですが、実際には需要を形成するためのレバーなのです。もし価格設定がサプライチェーンの管轄外に置かれるなら、供給を需要に合わせるための主要な手段が棚上げされてしまいます。
最後に、通常使用されるスコアカード――サービスレベル、予測精度、稼働率、在庫回転率――は、診断指標ではなく目標として扱われがちです。これらは貨幣単位で示されるものではありません。これらを個別に最適化すると、限られた資源である現金、棚スペース、生産ラインの時間、注意力を巡る意思決定が分断されてしまいます。ポートフォリオには、ポートフォリオとしての尺度が求められるのです。
これらの落とし穴についての詳細は、『Introduction to Supply Chain』の章 The Future をご覧ください。そこでは、予測手法とコンセンサス・プランニングの限界について検証しています。
経済による整合
もう一つのアプローチは、一見非常にシンプルです――整合を経済的な問題として扱うことです。顧客に提示する価格も、自社のボトルネックに付随する内部の「シャドウプライス」も、会議よりも効果的に選択を調整します。もしドックのスロット、ピッキングの波、またはキャッシュデーに、その機会費用を反映した内部価格が設定されれば、各部門間のトレードオフが比較可能なものとなります。営業はより多くを要求でき、オペレーションはイエスかノーを判断し、財務はどちらの選択にも利益の論理を見出すことができます。
この見方では、予測は最終的な判断ではなく、入力情報に過ぎません。予測は、起こりうる事象や需要の裾がどれほど深刻かを示してくれますが、意思決定を左右するものではありません。意思決定とは、我々が知っていることと、不確実性について信じる内容に基づき、次の資本または能力の単位を現在利用可能な最も価値のある機会に配分することなのです。
明日の需要は部分的に今日の意思決定によって引き起こされるため、価格設定はサプライチェーン内に取り込むべきです。価格が動けば需要も動き、需要が変化すれば供給もそれに応じるべきです。価格を第一級のレバーと位置づけることで、システムは計画に定期的に従うのではなく、常に自律的に調整を行うことが可能になります。
この立場の背景にある仕組みに興味があるなら、本書の章 Economics でその議論が詳細に展開されています。
実際にはどのように見えるのか
実際、整合は、意思決定エンジンから生まれます。このエンジンは、「もう1単位購入する」、「パレットを再配置する」、「生産オーダーを前倒しする」、「価格を変更する」といった、数多くの小さく具体的な動きを評価します。各動きには、ストーリーが添えられるのではなく、価格が付けられます:不確実性と機会費用を考慮した際の期待される貢献度はどの程度か?このエンジンはこれらの動きをランク付けし、常に最良のものを選び出します。どの単一の数値も未来を予測するわけではなく、代わりにマイクロな意思決定のポートフォリオが、状況の変化に応じて適応していくのです。
待機することもまた正当な行動です。なぜなら、待つこと自体に価値があるからです。今決断することで明日のより良い選択肢を失うのであれば、「まだ何もしない」という判断は「今すぐ何かをする」という選択に勝る可能性があるのです。延期は優柔不断ではなく、選択肢を保持する行為であり、他の資本や能力の使用と同じ基準を満たすべきなのです。
評価の尺度は貨幣に戻ります。サービスレベル、予測精度などは、目的地ではなくダッシュボード上の道具として役立ちます。重要なのは、一連の意思決定が企業全体の制約ポートフォリオにおけるリスク調整後のリターン率を向上させるかどうかです。もしKPIが改善しても経済的な成果が伴わなければ、そのKPIは誤った方向へ導いていることになります。
不確実性の表現方法、内部価格の明示、競合する動き間の調整方法など、具体的な仕組みに興味がある読者は、『Introduction to Supply Chain』の章 Decisions でその詳細に触れることができます。
SDAに対する立場。 もし「供給–需要の整合」が予測を巡る合意を意味するのであれば、私は賛同しません。合意は現金ではありません。逆に、不確実性の中で最も価値のある機会に希少な資源を割り当てることを意味するならば、私は全面的に賛成です――そのメカニズムは儀式的なものではなく経済的なものなのです。価格をサプライチェーン内部に取り入れ、予測は参考情報にとどめ、決して最終判断とならないようにしてください。期待されるリスク調整後のリターンに基づいて具体的な動きをランク付けし、最良のものを常に実行する――これこそ実を結ぶ整合なのです。