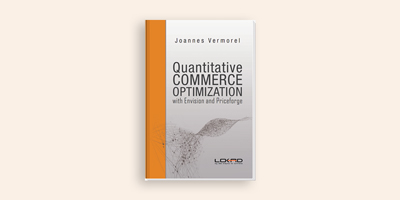結局のところ、たった一つだけ
在庫レベル(stock levels)や価格、取扱商品の構成の最適化に関しては、商人は適切な運用判断を下すために、多くの業績指標を確認する必要があります。しかし、統計的予測のように、数値的最適化は非常に直感に反するものです。特に、ビジネスのある側面を最適化するために指標を利用する際には、深く繊細な落とし穴があります:結局のところ、たった一つだけしかありません。最適化プロセスから導かれる最終決定のために複数の指標を維持することは、後付けで経営が良く見える指標を選び、ビジネスに損害を与える結果を招きます。さあ、この全体の展開を見ていきましょう。
商取引で一般的に見られる指標は数多く存在します。例えば、総在庫価値(低いほど良い)、平均在庫サービスレベル(高いほど良い)、総売上高(高いほど良い)、平均粗利益率(高いほど良い)などです。各指標を単独で見ると、すべてが単純で、明白な「改善」の方向性(例:高いほど良い)が示されます。しかし、同時に複数の指標を考慮すると、事態は非常に複雑になってしまいます。
実際、これらすべての指標は互いに矛盾しています:在庫価値を下げることはサービスレベルに悪影響を与え、粗利益率を上げること(ほぼ常に)は売上高に悪影響を及ぼします。したがって、_一度に一つの指標だけを改善する_という考え自体が無意味であり、その一つの改善はほぼ常に他の面の悪化を伴います。そして、大企業においては、企業構造そのものが問題を増幅させます。供給網部門は在庫増加に対して責任を負う一方、カスタマーセンター部門は顧客満足度の改善により評価されるのです。
しかし、問題は単に矛盾する指標を管理するだけではなく、時間も重要な要素です。なぜなら、市場状況は常に変動しており、多くのノイズが伴うからです。その結果、経営陣が何をしていても、四半期ごとに(ほぼ)必ず改善される指標が存在します。したがって、見た目を良くするために、最も重要と見なされる指標を都合よく選び出す誘惑に駆られます。非常に技術的に聞こえるかもしれませんが、これは事後合理化、すなわち物事が起こった後に、すべてが計画通りに進んだ理由を説明する良い物語を作り上げる行為なのです。
したがって、事業最適化の取り組みが行われる際には、関連するすべてのビジネスドライバーを統合する「一つ」の指標だけが存在し得ます。例えば、在庫最適化に関しては、ピンボール損失関数が、需要の過大予測と過小予測の間に存在する非対称性を適切に反映する指標を構築するための第一歩となります。未来の需要に関してのこの非対称性を捉えるとともに、ピンボール損失は在庫状況のすべてを語るわけではありませんが、トレードオフ、すなわち「在庫価値」と「サービスレベル」の間のバランスにおいて、妥当な結果をすでに示すことができます。この「マスター」指標を持つことこそが、ほぼすべての物事を最適化する唯一の方法なのです。なぜなら、矛盾する指標を自由に選び出す余裕があると、すべてが曖昧になってしまうからです。
それにもかかわらず、「マスター」指標が不可欠である一方で、他の指標をすべて廃棄する必要はありません。商取引は通常非常に複雑であり、この複雑さを把握するためには、多くの指標を用いて必要な洞察を得る必要があります。しかし、これらの指標はあくまで洞察を得るためのものであって、運用上の意思決定を左右するためのものではありません。
一つの効率的なマスター指標を作り上げることは困難です。この指標は、対象となる問題に絡み合うすべての異なるビジネスドライバーのバランスを適切に取らなければなりません。実際には、これは矛盾する指標の組み合わせと戦略的な「重み付け」変数によって構築された複合指標であることが多いです。これらの変数は、経営陣が自社のビジネスについて持つ最高の戦略的理解を表しています。実際、「成長を求めるべきか、あるいは利益率を重視すべきか」といった高度に曖昧な問いに対して、定量的な答えは存在しません。
マスター指標を設計する際によく見られる落とし穴の一つは「素朴な合理主義」です。これは、完全に形式化されているにもかかわらず、ビジネスの本質的なドライバーの一部または全部を捉えていない指標を指します。その結果、そのような指標を改善することは、誤った方向に向かって加速するようなものです。素朴な合理主義は、関係者に誤った安心感を与える危険があり、俗に「大雑把に正しい方が、正確に間違っているよりもましだ」と言われる所以です。