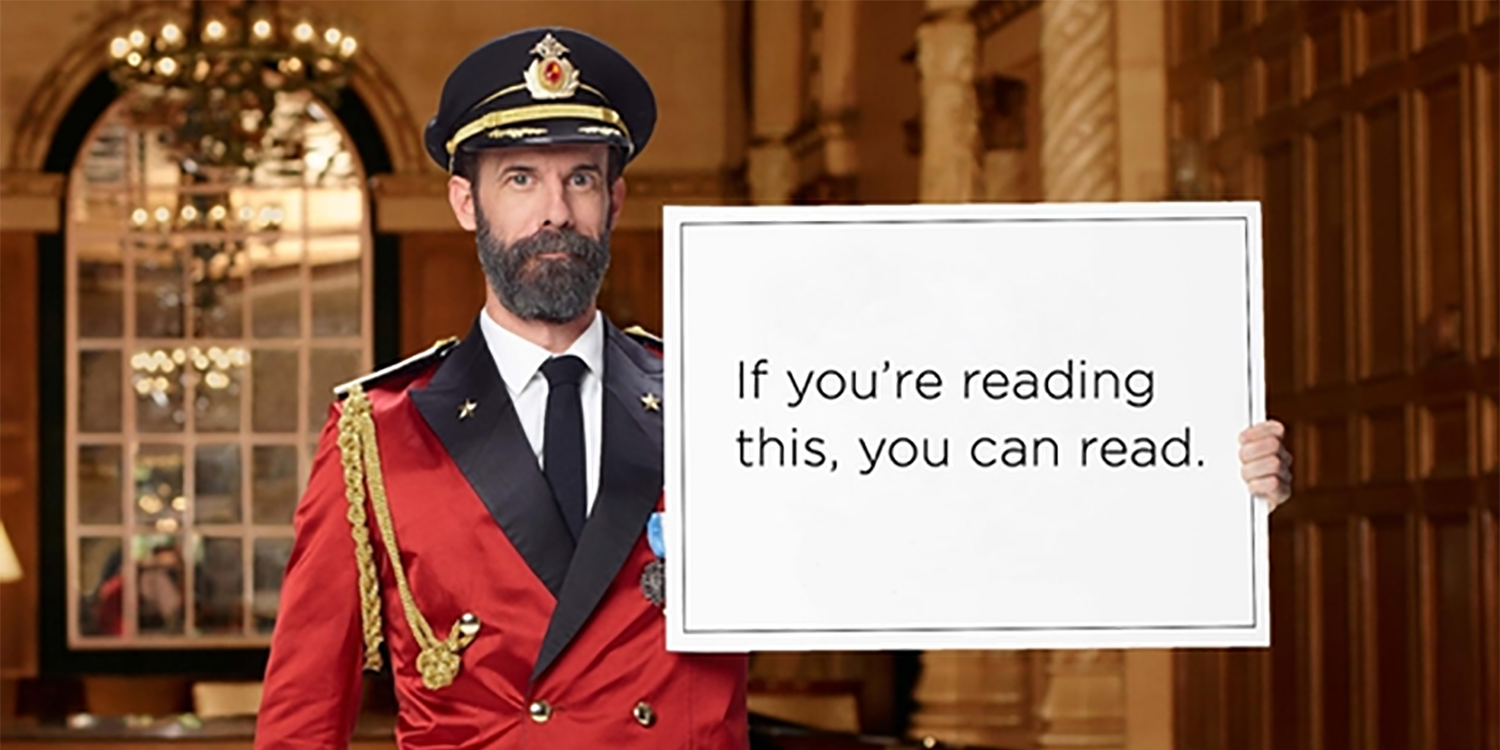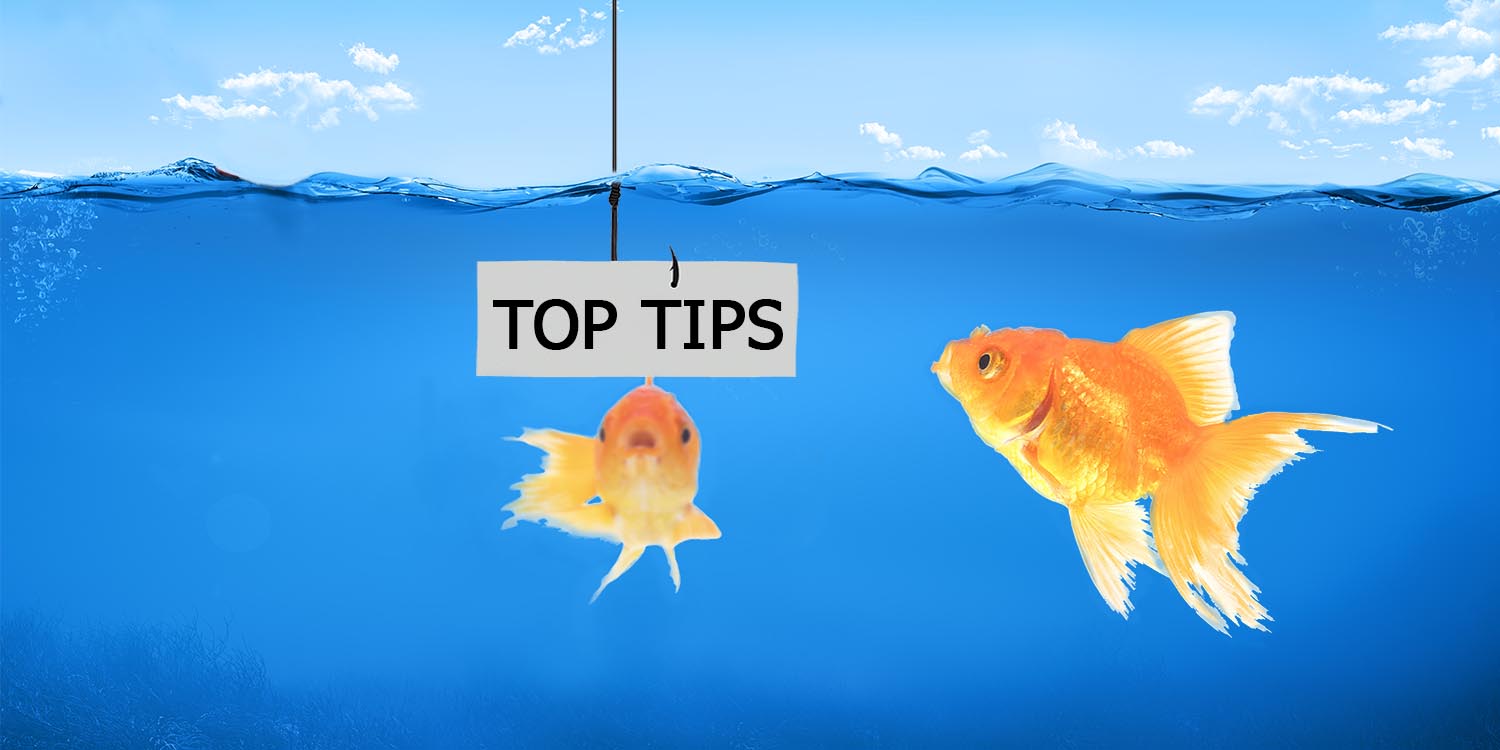サプライチェーン物語: ブルウィップの仕事
2004年に私の最初のプロとしてのサプライチェーン経験がありました。当時、私はパリにある大学、エコール・ノルマル・シュペリウール(ENS)のコンピュータサイエンスの学生でした。私の興味は完全に理論的な幅広いテーマにわたっていましたが、それらの理論を実際に試すという考えにも魅力を感じていました。理想的な計画は、そのような取り組みに対して報酬を得ることだと考えました。しかし、私はお金にあまり興味がありませんでした。ENSの学生は既に国家から給料を受け取っており――これは非常にフランス的なことで――それでもスポンサーがいれば時間を完全に無駄にすることはなかっただろうと思ったのです.
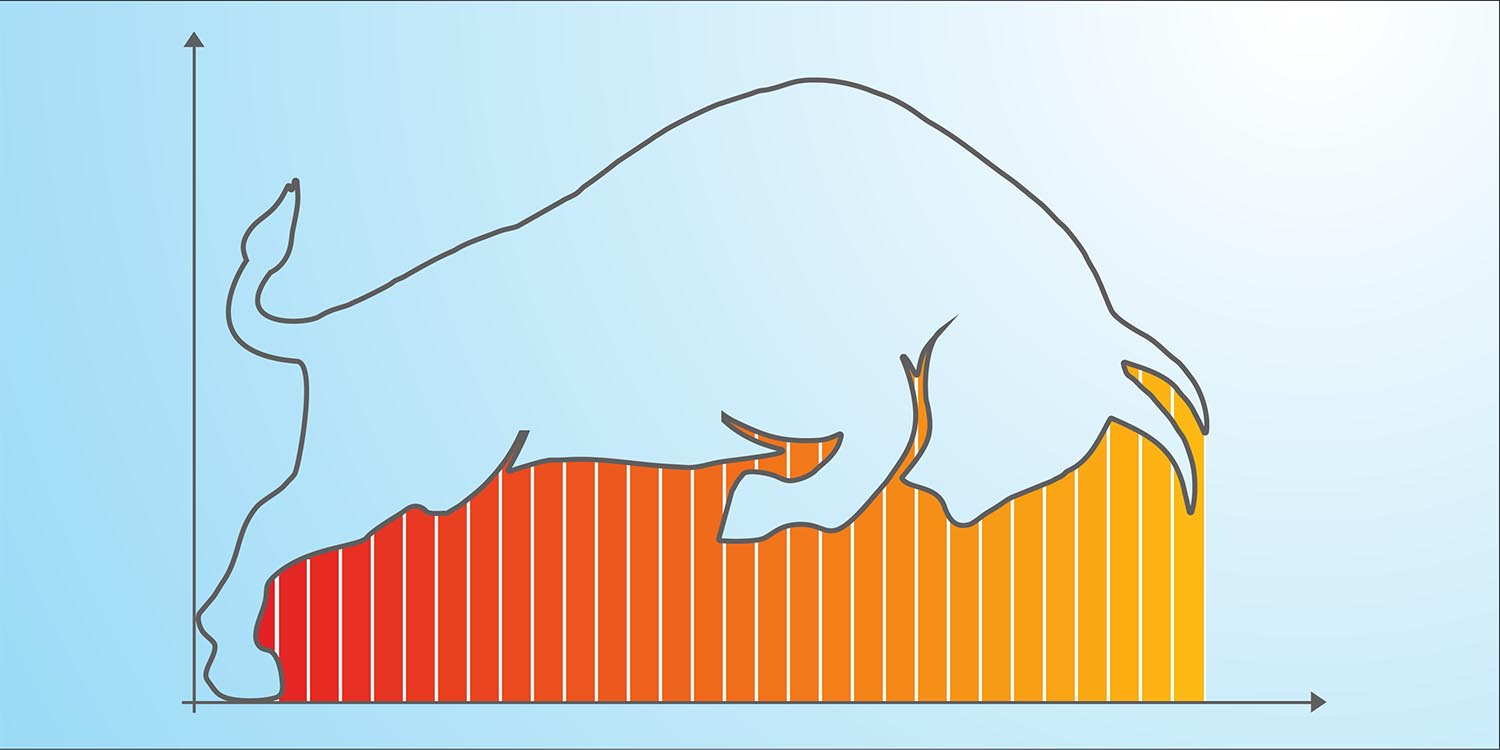
そこで、次のステップはそのようなスポンサーを見つけることでした。私はあちこちに尋ね始めました。それは実に奇妙な経験となりました。実際、ENSの目的は国家に仕える公務員を育成することにあります。私のキャリアはこの点で計画通りには進みませんでした。そのため、民間セクターとの連絡を求める試みは(控えめに言っても)好意的には受け入れられませんでした。それにもかかわらず、最終的にENSには「秘密の」ジュニアエンタープライズ、The Institute of the ENSが存在することを知りました。その名前は何も示唆しておらず、これこそがおそらく真意であったのでしょう。ジュニアエンタープライズは、学生にホワイトカラーの短期間の仕事を提供する非営利組織です.
インスティテュートの初代秘書である感じの良い中年の男性が私を迎えてくれました。彼は、数ヶ月ぶりに現れた初めての学生だと話し、私に渡す仕事は何もないと告げました。それは残念な知らせだったので、私は話を続けました。彼はこの微妙な問題について、名誉会長に相談することを決めました.
インスティテュートの名誉会長は、実際には100億ユーロ以上の食品小売ネットワークの社長であることが判明しました。数日後、私のケースを検討した上で、彼は自身の会社での請負契約の仕事を私に提供しました。仕事内容などの詳細は後で他の担当者が詰めることになっていました。私は同意し、すぐに彼のサプライチェーンディレクターの手厚い管理下に置かれました.
サプライチェーンディレクターは多忙な人物でした。60代になっても鋭敏で健康な彼は、大手コンサルタント主導の大規模なイニシアチブを進行中でした。そのイニシアチブのコードネームは「ブルウィップ」で、数年前に発表された影響力のある論文「The Bullwhip Effect」にちなんでいました。フランスのチームはこの件について、特別なコーチングセッションを受けるためにアメリカまで飛んでいったのです。当然、私はその論文について何も知りませんでした。ディレクターは急いで私に最新の状況を説明し、小売ネットワーク全体のフローに関するいくつかのデータを見せてくれました.
サプライチェーンについてはほとんど何も知らなかったものの、人間がランダム性をどのように認識するかという点には興味があることが分かりました。この研究分野で最も不可解な科学的成果の一つは、人間が平均して「統計的ノイズ」を識別するのが非常に苦手であるということです。私たち人間は、どこにでもパターンを見出そうとする傾向があるのです.
このようにフローの変動は非常に大きかったものの、その根本原因について私は直ちに懐疑的になりました。その懐疑心をディレクターと共有し、変動は単に需要のランダム性だけで説明できると主張しました。オリジナルのブルウィップ論文に挙げられた4つの要因のどれも、小売ネットワークが直面している問題に大きく関与しているとは思えなかったのです.
ディレクターは納得しなかったものの、私を忙しくさせ、何よりも自分の多忙なスケジュールから私を解放する良い機会と見ました。彼は私にプログラミングができるか尋ね、私はできると答えました。そこで彼は、このランダム性の仮説を検証するために私が実装するシミュレーターの作戦を説明し始めました。ネットワークとその品ぞろえを特徴づける約12のマクロパラメータという少量のデータで十分でした。会議全体は1時間にも満たず終了し、私は解散されました.
数週間後、私はシミュレーターを実装し、驚くべきことに、現場で観察されるのと同等のフロー変動が現れました。その根本原因は、取扱製品のストックアウト、すなわち傷みやすい製品に起因する平凡な現象でした。ストックアウトは、供給業者から倉庫へ、そして倉庫から店舗へと向かうすべてのフローに、微小ながらも一定の同期圧力を生み出していました。何らかの積極的な対抗圧力がなかったため、小さなランダムな波が最終的には大きく、しかし依然としてランダムなフローの波となってしまったのです。そこで再び会議が開かれました.
彼は私の結果を注意深く検証し、実装の詳細について次々と質問してきました。私の回答は彼を納得させるものでした。彼は私に、別の仮定に基づいたいくつかの反対実験を行うよう指示しました。数日後、私は追加の結果を持って戻ってきましたが、大局は変わらず、反対実験の結果も共に期待していた通りのものでした。まだ気づいていなかったのですが、これが彼と数年間にわたって持つ最後の会議となるのでした.
翌日、コンサルタント全員、私も含めて解雇されました. 新たなモットーは『原点回帰』でした.
この大規模なイニシアチブは、ブルウィップ効果の根本原因に対処すれば悪影響が解消されるか、少なくとも大幅に軽減されるという、現在では否定されている前提に基づいて開始されたものでした。期待されていた利益はすっかり消え、上層部は激怒しました。彼らの視点では、自分たちは騙されたと感じたのです。さらに皮肉なことに、この全体を論破するのに必要だったのは、たった一人の学生の偶然の貢献だけだったのです。反発は迅速かつ激烈に襲いかかりました.
この経験―私の最初の仕事から―私は最初のコンサルティング給与を手に入れ、そして「Primum non nocere」(まずは害を与えるなかれ)が単なる医療原則に留まらないという確信を持つに至ったのです.