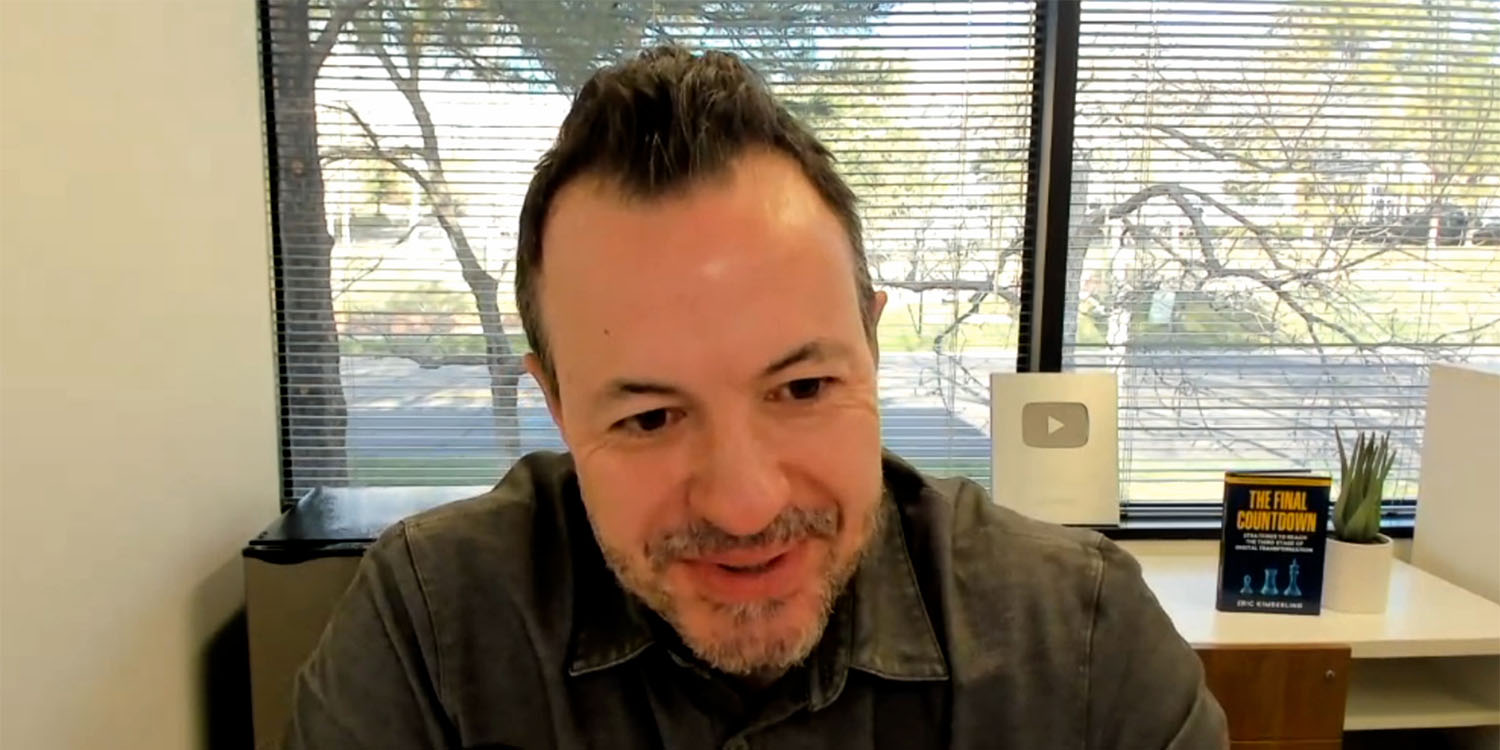00:00:00 サプライチェーン最適化の概要とトヨタの事例
00:07:28 経営層への価値の伝達;意思決定と資金
00:12:45 デジタルトランスフォーメーション:大規模な複雑性の簡素化
00:17:49 最新のサプライチェーン手法と言語の採用
00:24:00 フィルタリングされていないデータと生産準備におけるエッジケース
00:29:44 意思決定の向上:異議、混乱、そして予測
00:34:05 安全な意思決定とサプライヤーリスクの管理
00:36:23 模擬問題とサプライチェーンにおける現実の不確実性
00:41:13 経営層の権限強化、シナリオテスト、ROI
00:46:10 ビジネスへのインパクト:精度指標を超える
00:49:45 需要は設計される:付属品、予測、そして履歴
00:55:01 最適化の共同執筆と関係性の価値
01:00:51 ステークホルダーの調整、文化、そして経営戦略
01:09:29 デジタルトランスフォーメーションの推進とKPIの変更
01:15:19 ソフトウェア、インセンティブ、そして大手企業からの教訓
01:21:17 オーディエンス、言語、効果的なコミュニケーション;書籍のアドバイス
要約
LokadTVのインタビューで、Conor Dohertyがホストを務め、LokadのCEOであるJoannes Vermorel、Adam Dejans Jr、およびトヨタのJohn Elamが出演し、供給チェーン最適化が中心テーマとなりました。この対談では、グローバルな供給チェーンにおける意思決定について探求し、文化的変革と複雑なプロセスの簡素化が強調されました。Adam Dejans Jrはシステム全体の再考の必要性を強調し、John Elamは運用規模が複雑さの原因であると指摘し、望ましい成果に合わせた言語の整合性を重視しました。この対談は透明性と信頼構築の重要性を強調し、徐々に複雑さを取り入れることを促しました。経営層を引き付けるためのコミュニケーションの簡素化、さまざまな文化的アプローチの紹介、そして既存の慣行を変革するための継続的な学習の重要性について、洞察が共有されました。
詳細な要約
Conor Dohertyがホストを務めたインタビューで、私たちは供給チェーン最適化の複雑な領域に深く踏み込み、LokadのCEO Joannes Vermorel、Adam Dejans Jr、およびトヨタのJohn Elamを迎えて議論を展開しました。このディスカッションは、勤勉かつ明快に供給チェーンの最適化に関する多面的な探求を明らかにします。
対談は、グローバルな供給チェーン変革における意思決定への問いから始まります。Adam Dejans Jrは、変革は単なる自動化を超え、文化的変革や混乱への適応を必要とすることを強調します。彼は、プロセスの単なるアップグレードではなく、システム自体の再考の重要性を説いており、その考えは、ジョブ分割によって大企業に生じる複雑さを指摘するJoannes Vermorelによっても共鳴されます。Vermorelは、この複雑さに対して簡素化が重要な対抗策であると主張しています。
John Elamは、問題そのものではなく、運用規模が複雑さの原因であることを指摘することで議論を豊かにします。彼は、特に経営者を説得する際に、望ましい成果に合わせた言語の整合性を求めています。Adam Dejans Jrは、この見解をさらに推し進め、信頼構築のために複雑さを徐々に導入することを勧め、意思決定の流れを複雑化する政治的障壁の役割を強調しました。
鋭い比較を通じて、Joannes Vermorelは、政治的課題にもかかわらず効率的な慣行を取り入れているSpaceXなどの競合他社について語り、業務の効率化を拒む企業は存続の危機に直面すると断言しました。一致した見解として、政治的視点とビジネス視点を理解し統合することが重要であるとの認識が生まれました。
対談が経営層を対象とした最適化の議論に進むにつれ、ElamとDejans Jrは、純粋な技術用語だけでなく、不確実性を受け入れ、計画を財務指標と整合させることの中心性を再確認します。彼らは、シンプルなモデルから始め、徐々に複雑な層を導入することで、透明性を促進し、関係性を構築して最適化フレームワークの受け入れを得ることを提唱します。
Lokadのアプローチを検証する中で、Joannes Vermorelは確率的な予測に重点を置き、技術的手段よりも成果を優先する必要性を説明します。特にエッジケースに対処して包括的な生産レベルのソリューションを確保するために、意思決定を反復し洗練させる重要性を強調しました。
John ElamとAdam Dejans Jrは、トヨタの業務と類似点を見出し、複雑な供給チェーンの理解と管理責任全体でのプロセスの検証に焦点を当てました。彼らは、部分的な理解にもかかわらず、客観的なパフォーマンス改善を通じた信頼構築、透明性と実践的な戦略の融合の重要性を強調しました。
Conor Dohertyの問いかけは変革管理の探求へと続き、John Elamは意思決定における不確実性の統合を説明するために模擬問題を取り上げました。このアプローチは、Adam Dejans Jrが販売代理店向けに関連性のある提案を作成した経験と相まって、関心の薄い経営者との関わりにおいてシンプルなコミュニケーションの有効性を浮き彫りにします。
対談は文化的管理手法に焦点を移し、米国のテック企業とフランスの慣行のスタイルの対比を通じて、企業ダイナミクスに与える異なる影響を示しました。既存企業におけるレガシーシステムを克服し、革新的な変化を推進するためには、新たな創造的リーダーシップの手法が重要であると浮かび上がりました。
重要な側面として、経営者との効果的なコミュニケーションのために言語を簡素化する点が挙げられます。John Elamは修辞学とテクニカルライティングを教える中で得た洞察を共有し、受け手や文脈に合わせてメッセージを適応させることでエンゲージメントを向上させました。この議論は読書の推奨で締めくくられ、継続的な学習と適応の価値を強調しています。
インタビュー全体を通じて、技術的専門知識と経営層の意思決定を橋渡しするための深い洞察が浮かび上がりました。これは、謙虚さ、戦略的なコミュニケーション、そしてサプライチェーン最適化の分野における実体的成果のための絶え間ない追求によって支えられた、複雑さを乗り越え協力的な進化を促す旅路です。
完全な書き起こし
Conor Doherty: みんなが成功したサプライチェーン最適化を望む一方で、特に経営陣を含むすべてのステークホルダーがその意味を正確に理解しているかどうかを確認するための時間を取らないことがよくあります。さて、幸いなことに、今日のパネルではまさにそのトピックを議論します。今日、私と一緒に参加しているのは、トヨタからのAdam DejansとJohnny Elam、そしてスタジオにいるLokadの創設者Joannes Vermorelです。
Now before we get to the panel, you know the drill: like the video, subscribe to the YouTube channel and follow us on LinkedIn. And with that out of the way, I give you today’s panel.
ええ、Adam、John、とても参加していただきありがとうございます。これまでのLokadTVでの中で最速の対応かもしれません。なぜなら、数週間前にAdamに連絡を取ったところ、既に参加していただいたからです。参加してくれてありがとう。
Adam Dejans Jr: お招きいただきありがとうございます。ここにいられて嬉しいです。
Conor Doherty: John、まずはあなたからお願いします。LokadTVの視聴者の皆さんに、あなたの経歴とトヨタでの役割について紹介していただけますか?
John Elam: 私の名前はJohnny Elamです。現在、トヨタではビジネス・インサイトおよび戦略のマネージャーを務めています。ある意味、テックリードやプロダクトオーナーのような役割を担い、サプライチェーンの機能を支える三つの異なるプロダクトを担当しています。
さまざまな機能が存在します。需要予測、供給遂行などがあります。さらに、過去の販売データを通じて人々の好みを理解しようとするカスタマー・プリファレンス・エンジンもあります。こうして私は、これらの機能を支える三つの異なるチームを管理しています。私の経歴は、アプリケーション開発者、データアナリスト、データエンジニアとしての経験を経て、自然なキャリアの流れでプロダクトオーナーになり、自分の技術的知識を広範なビジネスビジョンに結びつけるに至りました。ここにいられることを楽しみにしています。
Conor Doherty: Adam、あなたもトヨタで働いていますが、あなたはミシガンに、Johnはテキサスにいると聞きました。では、Adam、トヨタにどのように入社されたのか、そして具体的にどのような役割を果たされているのですか?
Adam Dejans Jr: ええ、私の経歴は数学とオペレーションズリサーチにあります。デトロイト生まれということもあり、しばらく自動車産業でキャリアを積んできました。要するに、Fordで働いた後、コンサルティングも経験し、その後、時間を貸すのではなく製品の所有権を真に担うためにToyotaに入社しました。
現在Toyotaでは、プリンシパル・ディシジョン・サイエンティストとして働いています。主にJohnと共にサプライチェーンの変革に取り組んでいます。私自身はミシガンにいますが、ミシガンセンターで働いているわけではなく、現時点ではリモートでテキサス本社に所属しています。
私の主な役割は、Johnが担当している多くのプロダクトに技術的な視点から取り組むことです。具体的にはシステム設計や、各種アルゴリズムおよびプロダクトの数学的基盤の構築を担当しています。私たちの目標は、北米のサプライチェーンの変革を通じてグローバルに影響を与え、そこで得た知見を世界展開に活かすことです。現在、私たちは大規模なデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいます。
Conor Doherty: ありがとうございます。イントロダクションもありがとうございました。全国的、さらにはグローバルな変革について語る際、意思決定はどのように位置付けられるのですか?これは、LinkedInでAdamが頻繁に投稿しているトピックでもあり、あなた方の焦点は常に意思決定に置かれているからです。では、説明いただいたサプライチェーン最適化の中で意思決定はどのような役割を果たすのでしょうか?
Adam Dejans Jr: 一番大切なのは、これは本当に文化の変革であるということです。特に長く続く企業にとっては。例えば、現在のToyotaでも多くの工程が手作業です。変革を始める際、人々はまず既存の工程を自動化しようとします。
つまり、順番に手作業で行われているこれらのステップすべてを自動化しようとするのですが、それだけでは十分ではありません。それは単なる自動化であり、真の変革ではありません。変革にはシステム全体の再考が必要です。これらの工程は、コンピューターが引き継ぐ現状の形そのままではなくなるかもしれません。システムがどのように機能すべきかを判断するために、まず達成すべきビジネスメトリクスを設定し、次にその指標を達成するために必要な意思決定を行い、最後にシステムで何が起こり得るか、そしてその障害からどう回復するかを考えるのです。
私たちは、パンデミック、港湾ストライキ、部品の供給不足などの問題に直面しています。部品が到着するはずなのに届かなかったり、不良品のバッチがある場合、次に何をすべきかをどのように判断するのでしょうか?どのようにして、知的かつ自動的に、リアルタイムで適応できるような形でその決定を下すのでしょうか?
John Elam: また、管理の境界について現実的な視点を持つことも重要です。私たちはアメリカを中心に管理を行うグローバル企業ですが、その外ではリクエスト制となっています。日本が母船として、多くのグローバルに管理される要素、例えばエンジンやその他の戦略的供給資源に関する決定を行っています。私たちは、Toyota Motors EuropeやToyota Motors Asiaと、世界に分散する供給を巡って競争しています。
意思決定の一環として、実際にどの決定が可能かを見極める必要があります。ある決定ができれば素晴らしいのですが、現時点ではそれが不可能な場合もあります。自分たちの価値を証明し、成長し、世界にどのように貢献できるかを示すことが重要です。小さく始め、自分たちの限界を認識することが鍵です。現実を理解せずに夢だけを描くと、行き詰まってしまいます―いくつかの決定は可能ですが、制御の及ばない事柄も存在するのです。
Conor Doherty: Joannes、後ほどあなたにも伺いますが、まずはJohnにお伺いします。Toyotaが大規模で確立された成功企業である中で、Adamが示す方向に人々をどう向かわせるのですか?従来のサプライチェーンの意思決定の方法から、より最適化やオペレーションズリサーチに基づく方法へと移行するにはどうすればいいのでしょうか?
John Elam: これは、どのプロジェクトにおいても共通する答えですが、多くの技術者が耳を傾けたがらない、厳しい現実です。彼らがいる場所に合わせるのです。もし彼らが平均、中央値、最頻値の世界にいるなら、その言語を使ってコミュニケーションを取るべきです。彼らが何を知っているかを把握し、その言語で語りかけるのです。誰も新しい言語を学びたいとは思いません。
私はポルトガル語を学びたくありません;それなしでも成功した生活は送れます。もちろん、ポルトガルでは役立つかもしれません。地域に応じた生存のための言語はありますが、すべての人がそれを必要とするわけではありません。若いエンジニアとして新しいことを学ぶ中で、ほとんどの人は数学やツールに関心がなく、それが自分たちの世界で何を実現できるかにこそ関心があると実感しました。
ビジネスリーダーにとって重要なのは、お金です。どれだけの利益が得られるか、どれだけの時間を節約できるか、などです。私は自分の専門用語を脇に置き、彼らの言語を採用して理解を深めます。もしかするとより良い方向性を知っていても、彼らの言語を用いてそれを示すしかないのです。これが人々を前に進める唯一の方法です。
Conor Doherty: さて、Joannes、あなたはこの点についてどうお考えですか?私たちはヨーロッパで活動していますが、北米と同様の経験があるのでしょうか?
Joannes Vermorel: はいともいいえとも言えます。大企業を見たときの私の見解ですが、ここでは大企業、デジタルトランスフォーメーション、そして意思決定といういくつかの要素について話しているわけです。では、これらの要素を組み合わせて考えてみましょう。
現実として、サプライチェーンにおける意思決定は非常にシンプルです。特定の言語を必要としません。例えば、仮にToyotaが年間5000万台のエンジンを生産できるとしましょう。これは仮の数字で、正確な数値は分かりません。
そして、その生産をどのように配分するかという問題が生じます。例えば、北米へ一定量、その他の地域へ一定量、といった具合です。つまり、実際の問題は資源とどのエンジンをどのように配分するかということに帰着します。もちろん、細かい部分はもっと複雑で、さまざまな種類のエンジンが存在しますが、実情としてサプライチェーンにおける意思決定は一連のシンプルなプロセスで成り立っています。
主にリソースの割り当てと移動に関するものであり、根本的には非常に抽象的なものではありません。理解するのが難しいということもなく、物理的で具体的な要素があります。しかし、大企業がこれを手作業で行おうと考えたとき、彼らは労働分業を組織せざるを得なかったのです。
そして、その結果、非常に単純な決定がなされ、会社内の20の異なる機能が部分的にその決定に寄与することになります。これは労働分業の結果に過ぎません。もし超知能のAIなどが存在すれば、この労働分業は必要なく、単一の存在が直接決定を下すでしょう。
そして非常に頻繁に、このような複雑さや言語の問題を見ると、私の見解では、これは主に労働分業の副産物であり、複雑性が爆発しているだけです。しかし、これは全く作り話であり、実際のものではなく、非常に大規模な組織を支えるために作られた人工的なものなのです。
そして非常にしばしば、問題となるのは、その複雑な層を通じて決定されている基本的な事柄を明らかにすることです。通常、そこで本当の驚きがあるのです。つまり、最終的には200人もの人々が関与していても、結局はたった一つの数字に過ぎないのです。そして、興味深いことに、もしコンピューターのように計算できるデジタルなものがあれば、必ずしも200人を関与させる必要はないと気づくでしょう。
ここで、私はその変革が非常に重要であると考えています。Lokadでは、労働分業によって非常に複雑化していたプロセスを、最終的にかなり単純なものに置き換えてきました。そんなに多くの人が関与する必要はありません。そして、これだけ多くの人が関与することで生じる問題群は、数値的なレシピを導入することで消滅します。
Conor Doherty: ジョン、何度も頷いているのを見ました。あなたの考えをお聞かせ願えますか?
John Elam: いや、彼は全く正しい。解決すべき問題の大きさゆえに、作り物の複雑さが存在するのです。例えば、私たちには約21,000もの異なる制約が組み込まれたツールがあるのです。
だから、人間がそれを管理することはありえないのです。以前は人間が管理していたにしても、本当の意味で管理していたわけではなく、むしろ「左から右へ動かす」というような単純な管理であって、「どうすればこの情報を再編してより良い決定ができるか」という管理ではありませんでした。
その情報を、人間が良い決定を下せるように整理する方法は全く存在しませんでした。ですから、適切な場所に適切なツールを導入することで、複雑さを切り裂き、単純なものに還元できるのを実際に見てきたのです。
ごもっともです。多くの場合、予測の世界では需要がどれだけあるのかを理解しようとし、割り当ての場合は物事を適切な場所に配置するための最適化を目指すだけなのです。実際の決定は、あなたが言ったように非常に具体的で、たとえばエンジンが工場に向かい、その車を作るために動いているのが見えるようなものです。
しかし、実際に起こっている事柄の数の多さが複雑さを生み出しているのであって、問題そのものではないのです。
Adam Dejans Jr: そこで、私も何か付け加えたいと思います。既に述べたように、一連の決定があるのですが、そのプロセスの一つの問題は、その流れが異なる管理の柱の下にあるということです。
それは組織内の異なる部分に属している可能性があり、彼らはあなたが入ってその一部すら学ぶことを許さないのです。ですから、解決策を考え出せたとしても、政治的にはうまくいかないのです。政治的な観点では、ほぼすべてを逆転させなければならないのです。
一つの決定が20の部分に分割されているかもしれませんが、今度は5ステップずつ自動化し、次の5ステップをまた自動化する必要があります。そして、そのプロセスを徐々に進めていくのです。しかし、これは見過ごされがちな、政治的な側面の問題でもあります。
Joannes Vermorel: 全くその通りです。しかし、ここでの私のメッセージは、そうした政治的な側面に屈しないでほしいということです。具体例を見てください。非常に成功しているアメリカの企業、SpaceXです。NASAやアリアン・グループとは異なり、彼らはロケットのサプライチェーンを合理的に整理・統合することに決めたのです。
一見古典的に聞こえるかもしれませんが、実際にはそれほど革新的なものではありません。一般的に、現代のほとんどの企業はそのように組織されています。しかし、ロケットに関しては、ヨーロッパのアリアン・グループが実際に西ヨーロッパ全域にロケットの製造を分散させていたのです。
つまり、すべてのヨーロッパ諸国を満足させるために、50ヶ所でロケットを組み立てるのです。結果的に、NASAも自社のロケットで全く同じことを行っており、アメリカ国内の全ての州に製造工程を分散させていたのですが、それは完全に機能不全であることが判明しました。
その結果、非常に高価な価格で物を生産する組織が出来上がります。それは、競合相手が現れて「政治なんてどうでもいい、合理化するぞ」と決めるまではうまく機能していたのです。政治的なことは無視して、理にかなったことを行うのです。
私の見解では、競争相手からの圧力がそれほどなければ、ゆっくりと進めながら、各上司の権益や領域を維持する余裕があるということです。しかし、もし本当に追い詰められるような競合がいれば、そのような贅沢は許されないのです。
これは大きな課題であることに同意します。しかし、歴史的に見ても、非常に優秀であった多くの企業が、この変革に失敗したために倒産してしまったのです。競合は単に、ビジネスのやり方を劇的にでも単純化する方法を思いつき、突然低価格を実現したのです。
そして、古い企業はこの新しい環境では生き残ることができなかったのです。
Adam Dejans Jr: 同感です—本当に同感です。私の主張は、ビジネスの視点と個人の視点という二つの側面があるということです。
Joannes Vermorel: しかし、トヨタは非常に競争力があります。例えば現在、イギリスでは自動車産業がほとんど存在しなくなっているほどです。より現代的な生産方式を採用できなかったため、全てがドードー鳥のように消えてしまったのです。
Conor Doherty: さて、ここでいくつかのポイントをまとめて本題に戻りたいと思います。すなわち、特に経営陣を巻き込んで最適化を進めることです。その重要な要素の一つは、不確実性を受け入れることにあります。ジョン、あなたの現場、例えばトヨタやコンサルティングの仕事において、既存システム、確立された慣習、内部政治がある企業で、確率的な予測などの意思決定に関して、どのようにして自分の視点を受け入れさせるのですか?
John Elam: ええ、最初の回答と同じです。まず、彼らがどこにいるのかを把握すること、あなた自身はどこにいるのかを理解し、その言葉を学ぶことから始めます。しかし、その上で、誰かを決定論的最適化という考え方に引き上げることは、多くの人にとって全く新たな働き方なのです。そして、さらに量的供給チェーン・マニフェストや、時間の要素を加えるSDAのようなものとなると、それは全く別次元の話になるのです。
率直に言うと、多くの場合、私はそれらを段階的に追加していくだけです。まず、あなたがどこにいるのかから始めましょう。現状、彼らは古典的な最小最大在庫計画定義や、補充ロジックを用いています。正直なところ、これは多くの相互依存性があるため、最適なものを構築しようとすると局所的最適解に過ぎなくなるかもしれませんが、分割してコンテナ化できる何かを見つけ出せるはずです。それをPOCとして実証し、その価値を示すのです。
そして、それを彼らに関連付けるのです。率直に言えば、多くは単に会話をして彼らの言語を使うということです。彼らはドル、時間、安全係数に関心があり、p値や分散には関心がありません。半分以上のケースで、それが何を意味するのかさえ理解していないのです。不運な話ですが、まあそれが彼らの現実なのです。彼らが使う言葉は、市場シェア、利益、収益、ボリュームなのです。私たちは何年もそれを用いてきましたが、彼らはそのような用語を使っています。
そして、繋げて示すのです—おもちゃの例を作成しましょう。まずは「あなたの現状、そして私が考えるおもちゃの問題」、つまり小さくシンプルなExcelのようなものから始めます。それがどのように展開するかを示し、実際に稼働しているものを取り出して、しばらく並行して実行します。これがあなたのプロセスであり、これが私のプロセスです。特に決定論的最適化を行っていない場合、適切なモデルを構築すれば、その一撃で驚異的な成果をもたらすのです。
そして、そうすれば信頼が得られます。その信頼を得た後は、はるかに自由に実験を行えるようになります。そして、次の段階を取り入れていくのです。毎回、次の複雑さの層を加え、最終的には「時間をかけた最適化問題」や「時間を経た予測決定」の考え方という枠組みを理解してもらうのです。そうすれば、彼らはあなたの提案を拡大することを許してくれます。しかし、単に顔を出して説得するだけではダメで、それを実証する必要があるのです。
私が関わるプロダクトチームとよく話すことの一つに、速く進みたければ信頼が必要であり、信頼を得るには透明性が不可欠だということがあります。だからこそ、私が何をしたいのか、そしてどうやってそこに到達するのかを非常に率直に伝えているのです。多くの場合、彼らも応じてくれます。相互性バイアスは非常に強く、人々は自分の情報の一部を差し出すのです。多くは人間関係に起因しています。数学で答えを導けたらいいのですが、実際には人々に好かれること自体が戦いの九割を占めているのです。
Conor Doherty: ジョアンネス、改めて伺いますが、これはLokadでのあなたの経験とどの程度一致していますか?
Joannes Vermorel: Lokadでは、私たちは全く異なるアプローチを取っています。我々にとって、問題への取り組み方、特に技術的手段はほとんど重要ではありません。結局のところ、私たちは確率的予測を使っていますし、それで全く問題はありません。確率的最適化も同様です。言い換えれば、彼らが聞いたこともなく、知らず、気に留めず、時間も割かない多くの技術があるのですが、それで構わないのです。
私たちが目指すのは、それらの決定が明確に識別される状態に到達することです。生産割当、在庫割当、購買数量、さらには価格最適化(価格が上昇または下降するもの)など、さまざまなスコープがありますが、どれでも構いません。信頼を得るためのマイルストーンは、技術的に言えば、実運用に移行するための主要なマイルストーンである「0%の狂気」を実現することです。すなわち、理想的には数百万単位の決定を、巨大なスケールで生成する必要があるのです。我々は直接、巨大なスケールを目指します。
そして、その理由があります—実際、より容易で、より速く、より安価に実現できるからです。直感に反するかもしれませんが、ほとんどの統計手法はデータが多ければ多いほどうまく機能します。また、ERPからデータを抽出する際、もしフィルタリングしようとすると、より多くの論理が必要になります。ですから、フィルタリングを行わなければ、適切なツールがあれば実際にはシンプルになるのです。通常、フィルタリングは特にデータ抽出パイプラインにおいて多くの複雑さを生み出します。
ですから、我々はこう言います。我々はシステムと共に動作し、フィルタリングせずにすべてのデータを取り扱うのです。それで十分です。すべてが容易になるのです。そして、私が「0%の狂気」を持つ決定と言うとき、それは私たちが生成したすべての決定を見た人が、何の異議も唱えられない状態を意味するのです。
最初は反復的に進めます。なぜなら、人々は異議を唱えるからです。「ああ、この決定は興味深いが、これこれの理由で実施できない」と言われるでしょう。それならば、論理を変更して修正するのです。または、「ここでは注意が足りない。これはVIP顧客だ」と指摘されるかもしれません。おや、新たな概念、VIP顧客。知らなかった、という具合です。VIP顧客が存在するという文書がなかったのですね。もっと詳しく教えてください。なぜこの顧客がそれほど重要なのかを説明してください。了解です。では、VIP顧客を考慮に入れるように調整し、という具合に。洗い流して、繰り返し、反復します。規模に合わせて、最大パラメータで。
そして最終的には、数週間という時間の中で、人々が何の異議も唱えられないシステムが出来上がるのです。そこで信頼が生まれます。突然、彼らは非常に理解しやすい決定をただ生成するシステムを手に入れるのです。なぜなら、それはただの「決定」であり、誰も本当の意味で異議を唱えなくなるからです。
私たちにとって、これが信頼を獲得する方法です。通常、すべてのエッジケースや奇妙な事象を受け入れることによって、それが「POC」ではなく、実際に生産準備が整ったシステムという印象を与えるのです。たとえ技術的には単なるパイロットであっても、最大規模で、あらゆる奇妙な事象を網羅していれば、最適化の観点から完全でなくても構いません。ツールが素朴なものであっても、後回しにすることが可能なのです。私たちにとって初期の課題は、超最適化されたものを持つことではなく、誰も正当な異議を唱えられないシステムを持つことなのです。
John Elam: 私たちは似たような点に触れていると思います。「何かを切り取る」と言うときの意味は、トヨタのサプライチェーンには…とにかく、ここに来て三年経ちましたが、いまだに理解しきれない部分があります。私たちは4次、5次のサプライヤーさえ抱えているのです。工場で取り付けられる付属品、プラントで取り付けられる付属品、ディーラーで、あるいは車両流通センターで取り付けられる付属品もあります。そして、私たちから直接付属品を購入することも可能です。 そして、それは付属品に過ぎません。次にエンジンですが、私たちは世界中で製造しています。ですから、私が「POC」と言うとき、その意味するところは、そうした作業領域の一つを指しているのです。すべてを選別することはできません—なぜなら、互いに交差しているからです。それはまた別の問題です。私の付属品の予測を正確に行うためには、まず車両の予測を正確に立てなければならないのです。例えば、シエナに何枚のマッドフラップを取り付けるかを予測しようとするなら、いったい何台のシエナを製造しているのかが問題となるのです。
つまり、切り刻もうとしているようなものです—ええ、実際、どれに集中すればいいのか…泳ぐレーンに留まれるのでしょうか?そして、多くの場合、私が「泳ぐレーン」といったとき、それは正直に言えばマネージャーの責任を意味します。彼らの影響範囲には限界があるからです。だから、あなたの言う通りです。あなたが述べた中で私が本当に気に入っているのは、取り組むべき事柄のすべてのエッジケースをカバーしているという点です。そうです—そのものを作るのです。スイッチを入れれば、本番環境で使える状態になります。すべての問題を解決できるのです。
はい、その点については全く同感です。これを私は「体系的データ変換」アプローチと呼んでいます。つまり、物事にどう取り組むかというと、プロセスごとに進めながら組織全体を巻き込むのか、それとも組織の一部分だけで全プロセスを完結させ、そこから展開するのか。二つのアプローチが考えられるということです。
しかし、どの方法を取るにしても—プロセスごとに各販売部門を網羅する方法であれ、あるいは北米だけを徹底的にやる方法であれ、どのレーンを選んでも100%完成させる必要があります。なぜなら、それが信頼を得る唯一の方法だからです—自分が実際にあなたと同じ、あるいは多くの場合は客観的により良い成果を出していることを示すことで。そして、これが私のいうPOCの意味なのです。
というわけで、あなたの言う通りだと思います。ここで言うPOCは、サイエンスフェアの実験のようなものではなく、真にコンセプトが証明された状態を意味します。そして理想的には、POCが完了した時点で、本物のMVP(最小限実用製品)ができ上がっているはずです。これは実用可能な製品であり、ビジネスに価値を加えるものです。すべてのエッジケースが洗い出された後に。しかし、確かに、とても良いポイントです。私たちがJupyter Notebookを作って終わりだと人々に思ってもらいたくはありません。
Joannes Vermorel: ええ、まさにその通りです。ノートブックです。全くその通り。これこそが、私が何度も見てきた データサイエンス の落とし穴、というべきものです。あまりにも多くの、露骨に間違った行があり、業務を担当する人々、つまり最終的に意思決定の責任を負う人々がその数字を見ただけで、10行ごとに狂気を発見してしまうのです。全くもって常軌を逸しています。機能しないし、通用しないし、損害や複雑な問題を引き起こすでしょう。
そして、私にとってはそれが信用を完全に失う最速の方法です。どの技術が使われようと関係なく、意思決定を見直すマネージャーが極端な誤りを見逃さなければ、さらなる反復改良が必要になります。そして、異議がなくなるまで改善を続けるべきです。人々はその決定を見て、「もし同僚がそれをやっていたら、すぐに承認するだろう」と言うのです。おそらく、時が経てば、いくつかの決定が誤りであったことが明らかになるでしょう—再び言いますが、予測は完璧ではありません。しかし、現時点で私が持っている情報を考えると、すべて承認すべきだと思います。以上です。
John Elam: ええ、それは良い考え方ですね。良いメンタルモデルです。同僚はこれを合理的な予測または意思決定と見なすでしょうか?そして、もし彼らがその段階に到達できなければ、先に進むことはできません。まだ信頼を得ていないのです。
Joannes Vermorel: そして、異議が出るときには、モデル化の中に明らかに間違っている部分が必ず入っているものです。たとえば、仕入先に要求している購入数量は適正でも、倉庫での納品受け入れ能力が限られているという事実を忘れているといった、馬鹿げた点が挙げられます。そしてここで、衝突が起こるのです—同じ日にあまりにも多くの トラック が倉庫の入り口に到着するためです。ご覧の通り、注文量自体は正しくても、残念ながら別の、一見関係のなさそうな要因がそれを阻害しているのです。
改めて言えば、他にもたくさんの要因があります。そして、こうした異議はしっかりと取り込むことが非常に重要です。そうすることで、人々が「この数字は実現可能な範囲すらない。これやこれやあれも加味すると、全く実用的な解決策にはならない」という、極めて率直な異議を唱えなくて済むのです。
Adam Dejans Jr.: 僕の場合は、この件に関して、経営陣の心に響くような多くの質問をします。たとえば、「昨年の港でのストライキを覚えていますか?あれはひどかったですよね?」などです。そんな感じです。そして—お金を失うのは本当に嫌なものです。
実際、よく耳にするのは「予測の 精度 を向上させる必要がある」という話です。そして、私が彼らに説明したり、議論を交わして考えたりするのは、すべてが順調に進んでいるときは予測はかなり容易であるという点です。すべてが安定し、順調に進んでいれば、はい、場合によっては より正確 かもしれません。しかし、いざという時—例えば港でのストライキが起こった場合—その事態を予測することはできないのです。
ですから、最も予測が必要とされるのは、予測が失敗する時です。必要とされる時こそ、ちょうどそのタイミングで失敗するのです。では、その存在を回避して無かったことにするのではなく、受け入れてプロセスに組み込むのはどうでしょうか?それが、私が提唱しているアプローチなのです。ほとんどの場合、うまくいっています。ただ、これはゆっくりとしたプロセスです。非常に大きな組織にいると、変革を起こすのは非常に困難です。多くの場合、それは部門ごとに隔離されているためです。
しかし、それが狙いなのです—彼らが実際に経験した現実の例に関連付けるよう努めています。彼らが解決したいと思っている問題に対して、どう解決すればよいのかが分からない場合に。そして、その過程で、彼らが実際に経験した痛みのポイントに対処する機会を得るのです。
Joannes Vermorel: それは興味深いです。なぜなら、こうした混乱状態をモデル化するのはそれほど複雑ではないからです—単に「大きな供給側の混乱が年に5%の確率で起こる」と設定すればいいのです。バンッ。ええ、なぜ5%なのか?というと、昨世紀には二度の世界大戦に加えて多くの出来事があったからですね。最近になっても、大きな供給側の混乱が年に5%の確率で起こると言っても、それは決して非常に高い数値ではありません。そして、需要側や他の要素についても同様のリスクがあります。ですから、これらのパーセンテージは大部分が概算であって問題ないのです。
興味深いのは、だからこそLokadでは予測そのものを提供せず、意思決定に注力している点です。予測は理解するにはあまりにも複雑だからです。そして意思決定において—通常、この混乱状態に至ったときに—人々は「例えば、この決定、この在庫は少し高すぎる」と指摘します。そこで議論は、そうですね、本当にそれは高すぎるのか?といった点に発展するのです。問題が起こるかもしれませんが、それがあまりに高いと不合理ではないか、と。
そして興味深いのは、人々が持っている予測を見ると、同時に考えるのが非常に難しいということです—需要が100かもしれないし、50かもしれない、というように、状況が非常に不確かだからです。あらゆる可能な未来を考慮するのは非常に困難です。しかし、意思決定を見たときに人々は「はい、この決定は多数のリスクの集約だ」と言い、あなたも「まあ、少し保守的に見えるかもしれませんが、どうでしょう?サプライヤーの信頼性不足、遅延、港でのストライキなど、様々な問題が起こり得る。結果的に、これは安全と言える」と評価するのです。
そしてこれが興味深い点です:私たちが最終的な意思決定、たとえば資源の配分に関する議論に焦点を移すと、突然、特に経営陣はこの決定に私たちがあまり理解していない多数のリスクが組み込まれているという考え方に非常に安心感を覚えるのです—ただ一つのパッケージとして捉えられるのです。そして、これが従来の、奇妙なモダリティやファットテール事象を含む予測を伝えるよりも、はるかに効果的に機能するのです。
Conor Doherty: ええ、その通りです。まさに言おうとしていたのですが—すみません、次のポイントに移りますが、これはまたチェンジマネジメントの一部であり、ジョン、あなたはこの件について情熱的にお話しされますよね。しかし、その一環としては、単にユーザーの同意を得るだけでなく、実際にそれがどのように動作しているのかをある程度理解してもらいたいのです。ほとんどの場合、人々は「まあ、うまくいっている、十分だ」とだけ言いたくはなく、少なくとも「さて、確率分布は正確にはどのように機能するのか?それをどう意思決定に変換するのか?」というエグゼクティブサマリーを求めるのです。では、ジョン、まずはあなたにお聞きします—このチェンジマネジメントの部分、つまり、人々が内部で実際に起こっている複雑な数学をある程度理解できるようにするための対応を、どのように行っているのですか?
John Elam: 正直なところ、トイプロブレム(おもちゃの例題)は本当に素晴らしいんです。シンプルで分かりやすい例題というものです。例えば、地上在庫として保持すべき在庫量の意思決定に不確実性を組み込みたい場合—とりあえず、1%の確率があるという仮定を置いてみましょう。ご存知の通り、我々は月単位で車を注文しています(現在は注文頻度を大幅に上げるための取り組みをしています)が、今は月に一度車を注文しているのです。ですから、各月に例えば1%の確率で港でのストライキが発生する、と仮定しましょう。
さて—そして、その確率は変動する可能性もあります。例えば、契約期間が終了に近づくと、港でのストライキの可能性は高まるかもしれません。その可能性が上がるとして、私はそれを非常にシンプルにプロットするだけです。例えば、1%の確率から、例として10%に上昇する、といった具合に。そうして、その上昇を示すのです。そして次に、私は「見てください、各月ごとに、たとえ安全性を考慮するだけでも、おそらく1%分余分に車を注文する、もしくは一定数余分に車を注文して、いずれいつでもストライキが起こり得るという不確実性に対してヘッジすべきです」と言うのです。
現在のところ、その確率はかなり低いですが、契約終了が近づくにつれて上昇するでしょう。だからこそ、その非常に不確実な事象が発生する可能性が高くなると見越して、地上在庫を増やす必要が出てくるのです。そして、それを積み上げた後、シナリオは二通りあります。ストライキが起こらない場合と、起こる場合です。そして、結果を示すのです。「見てください、ストライキは起こらず、わずかに余分な在庫があった。翌月は、不確実性が低下したため、通常の在庫量に戻し、注文量を少なくした。そして、その余分な在庫をヘッジするために、翌々月まで余分な保管コストがかかった。つまり、数百万ドルものコストがかかった」といった具合です。
反対のシナリオを見てみましょう。つまり、ストライキが発生した場合です。そして、通常ストライキはどのくらい続くのでしょうか?2週間でしょうか?過去を振り返って、「通常、どのくらい続くのか?」と考えると、2週間、すなわち2週間車が一切届かない状態です。これはいったいどれほどのコストがかかるか、ということになります。そして、その二つの数値を示すのです。どちらのコストをより受け入れたいでしょうか?どちらかは必ず発生するのです。皆が同意できるのは、ストライキが起こるか起こらないかというのは明白な事実であるという点です。非常に単純です。そして、このトイ・エグザンプルにおけるさまざまな結果を示すことで、人々に分布や不確実性、さらには時間の経過とともに変化する不確実性について考えさせるのです。
トイExcelの問題は本当に素晴らしいのです。シンプルで分かりやすく、人々はそういったものを学びたいと思うものです。誰もが、賢くありたいと願っています。私もそうであり、あなたもそうでしょうし、我々は皆、賢くありたいのです。では、どうすれば彼らをその感覚に導けるでしょうか?必ずしもすべてを一々見せるのではなく、「さあ、一緒にこれを作り上げよう」という形です。もしPowerPointを使って登壇するなら、それは失敗です。ホワイトボードを使いましょう。一緒にホワイトボードに書き出して、共に学び、共に解決策を見出していくのです。
そして、私は彼らの抱える問題から始めるのが好きです—彼らはアクセサリー関連かもしれませんし、エンジンの発注をしているかもしれませんし、何を発注しているかわからないかもしれません。つまり、あなたの業界は何ですか?というところから始め、一緒に検討し、「どのような不確実性がありますか?」と尋ねるのです。すると「場合によっては、こんなこともあります」と答えます。例えば、「昨年、列車のストライキがあった。あれは大きな問題でした」などと。そこで、その2つの異なる決定のモデリングについて話し合うのです。そして、私が彼らの言葉を用い、彼らが導いてくれる—つまり、私たちは本当に協力して進めるわけです。私がこの考え方を持ち込み、彼らが実際に感じている痛みを提供する。これこそが、製品を作り上げる最良の方法です—実際に経験されている痛みを解消するために、ということです。
Adam Dejans Jr.: もう一つあると思うのは、彼らが「これはどう動作するのか?」と尋ねるとき、必ずしもアルゴリズム自体に関心があるわけではなく、実際に関心を持っているのは、どのレバーを操作して変更できるのかという点です。例えば、「これをテストできるのか?」という疑問です。一例としてシナリオテストがあります。彼らはシナリオテストが大好きです。「例えば、10%のところを50%に変えたらどうなる?」とか、「安全在庫をもっと追加できるのか?」といった具合です。こうした変更可能なポイント(レバー)があること、そして何が操作可能かを知っていることが、合意形成に大いに役立つのです。
Conor Doherty: ええ、その通りです。まさに、内在的統制の感覚、つまり、参加している実感を人々に与えるという点です。それについてですが、これは改めてあなたのアプローチと一致していますか?
Joannes Vermorel: 確かに類似点はありますが、私たちは全く異なる方法を取っています。Lokad流の典型的な方法は、私たちが「経済的ドライバー」と呼ぶ半ダースの要素で、各決定に装飾を施すことです。つまり、ケースに応じて、予測される 在庫コスト、品切れ のコスト、仕入先の遅延コスト、これやあれのコストなどが存在する—当然、部門によって異なるのです。
しかし、つまり、すべての決定には、懸かっているリスクのドル換算評価が半ダース伴うのです。そして、興味深いのは—先ほどの類似点に戻りますが—私たちは確実にドル換算でリスクを評価し、意思決定に異議を唱える際、人々にはそのドル評価に対して異議を述べてもらうようにしています。なぜなら、それが「そのコスト評価には賛同できない」という人々の声を引き出す手段になるはずだからです。
彼らは、我々がどのようにこの計算に至ったかその詳細には本当にこだわっていないが、通常非常に有用なのは「例えば、サプライヤーの遅延に対するドル単位のリスクがあまりにも低すぎる」という意見だ。これは非常に興味深い—もしかすると、我々がリードタイムを正しく見ていないからか、あるいは他の要素を考慮に入れていないからかもしれない。しかし根本的には—だからこそそのレバーに繋がるのだが—それは100回のシミュレーションを求める人々を一掃する方法の一つである。
実際には、むしろ「さて、何に関して―ビジネスのビジョンがどこにお金を使うべきかという点での乖離は何だ?」という感じだ。例えば、港でのストライキの場合は、それを支払わなければならない保険料と考えることができる。我々はこの保険のコストを正しく設定しているのか?我々が算出した金額は正しい範囲に収まっているのか?そして、ここで非常によく戻ってくる—シミュレーターや手法に対して、そのおもちゃの例に立ち返るが、通常、コストに立ち返って「さて、ストライキなどのリスクに対するこのコストは、概算で計算しても正しい範囲内にあるか?」という具合になる。
そしてまた、常識の範囲内にという条件がある—つまり、このコストは、我々が正しいと考える範囲内でなければならない。そしてそうであれば問題ない。しかし、もし我々が経済要因の一つを大幅に過大評価あるいは過小評価していると気付いた場合、修正が必要となる。
John Elam: 私はその表現が大好きだ—保険という言葉。なぜなら、まさにそれが本質だからだ。そう、本当に素晴らしい表現で、人々に「なぜこのコストを支払っているのか」を理解させる助けとなる。まるで賭けに対してヘッジしているかのようで、保険をかけているのだ。私はそれが大好きだ。
Conor Doherty: ありがとう。改めて、意思決定におけるROIの観点―つまり、意思決定を場合によっては保険と見なすというその考え方―は、いわゆる従来の意思決定アプローチから逸脱する可能性がある。例えば、アダム、あなたは以前「ただ精度を高めたい」と言っていたが、正直なところこのテーマは常緑の話題だ。私が展示会に出かけたり、潜在的な顧客と話していると、必ずこの話題が上がる。彼らは「私の痛みのポイントは、もっと高い精度が必要だということだ」と言う。だから、改めてアダム、まずあなたに伺いたい―どうやってその二つを分けて考えるのか?なぜなら昨日、LinkedInで「より良い決定はより良い予測よりも優れている」と投稿していたのを知っているからだ。
Adam Dejans Jr.: そこでの鍵は、何度も強調することにある。すなわち、予測を使って何をしているのかということだ。まず、どのビジネスメトリックを改善しようとしているのかを決定する必要がある。そして、その他のすべてはそれを支援するためのものに過ぎない。だから、最も正確な予測があっても、それをどう活用するか、あるいは使わないかで結果は変わる。
精度を追求するもう一つの側面は、まず第一に、物事は常に変わるため、決して100%の精度には到達しないということだ。この変化を意思決定のフレームワークに組み込む必要がある。しかしそれを超えて、例えば、95%の精度に達しているとして、そのコストを払ってまで96%にまで上げたいのか?そして、もしそのパーセンテージの向上がビジネスメトリックに結び付かないのであれば、データチームは実際のビジネスにどのような影響があるのかがわからない任意の精度指標を追い求めるだけになってしまう。
つまり、1%の向上でどれだけの利益が得られるのか―それを定量化できるのか?最終的にそれは、定量的な金額にどのように反映されるのか、どう活用されるのか、ということだ。これが、大企業、特にトヨタのような古参企業でよく見られる現象だ。トヨタは日本の企業で、一度もレイオフを行ったことがない。そして、そこは一生涯キャリアを築ける会社とされている。これまでの実績が彼らを今日の地位に導いており、そのやり方を踏襲することを好む。なぜなら、ナンバーワンの自動車メーカーである理由があるからだ。つまり、「もしこれまで通りにやり続ければ、同じ結果が出続けるだろう。では、これまでのやり方をより良くすればいい」といった考え方だ。
そして時には、前述のように、結局は何かを変えなければならなくなる。なぜなら、誰か他の者が現れて変化をもたらすからだ。と、少し話が長くなったが、そんな感じだ。
John Elam: 話したいのは、意思決定に焦点を合わせると、今まで以上に議論すべき点が増えるということだ。予測だけに集中する必要はなくなる。例えば、我々が構築した一つのツールはサジェッションエンジンである。これは全く予測に依存せず、予測を気にもしない。その目的は純粋に収益を増やすことであり、つまり車両により多くのアクセサリーを提案し、限界点まで販売を押し上げるということだ。
どれだけ速く売れるかについては正直なところ大きな問題ではなかった。測定の焦点は、平均的な販売速度を維持しつつ、車により多くの金額が付加されるかどうかという点だった。我々はパイロット群とコントロール群を対象に、ペアおよび非ペアのt検定を実施し、同一期間の過去の平均と比較した結果、はるかに多くの収益を得た。ここには予測は存在せず、その精度も問題とならなかった。
我々は実際に、好成績を収めているディーラーから成功の戦略をコピーし、それを業績に苦しむディーラーに貼り付けた結果、収益を増加させた。そして、その製品については「いつ予測するのか?いつ何をするのか?」と多くの質問を受けるが、私は「そんなことはしない。特定の機能を担当する者に対し、この推奨を実行すれば、おそらく同じペースで売れ、かつ収益が増加するだろう」と伝えるだけだ。それだけで、これが意思決定であり、非常にシンプルな決断であるが、ビジネスに貢献し、収益増加に直結するのだ。
だからこそ、完璧な予測に固執するより、どのような意思決定を下すかに注目する方が良い。なぜなら、数多くの意思決定が可能であり、正直なところ予測自体は付加価値を生み出さないからだ。予測が示すものに基づいて意思決定を行うことこそが、価値を生むのだ。だから皆、水晶玉を求めるが、結局そんなものは決して手に入らない。
Joannes Vermorel: 全く同感だし、車に適切なアクセサリーを事前に搭載するというあなたの例は、その顕著な例だ。主流のサプライチェーン観における予測の考え方は、需要を惑星の未来の位置のようなもの、つまり何があっても必ず起こると見なすものである。そしてもし0.00001%の誤差にまで絞れるとしたら、それはただの無意味な数字に過ぎない。ここであなたが示しているのは、需要は設計可能であり、もしより良い車をより高い価格帯で顧客に提示すれば、顧客はより高価でより良い車を購入するかもしれないということだ。
もちろん限界はある。ある時点で「本当に素晴らしい車だが、もう手が届かない」という声が上がるため、明確な上限は存在する。しかし、その限界を試す前に、テーブルの上に本来得られる利益を置き去りにしていることになる。そして問題は、もし過去において控えめにやっていた結果、顧客に十分な装備の車を提示できなかったという過ちを、そのまま予測が再現してしまうことにある。
これが、まさに惑星の軌道という考え方である—過去をただ眺めるだけのアプローチだ。しかし現実は、未来はこれから下す意思決定、すなわちその結果として生じるものであって、逆ではない。だからこそ、私は意思決定が予測よりも優れていると非常に強く信じている。大部分において、未来はこれから下す決断の結果、つまりその帰結であるからだ。
Adam Dejans Jr.: また、時にはリコールがあったり、部品やアクセサリーが不足したりして、過去6ヶ月間の歴史データから抜け落ちる場合がある。だから、それは今や誰もそれを望んでいないということになるのか?しかし、歴史的には需要が低下している、つまり「車にマッドフラップは不要だ」となっているが、これは明らかに真実ではない。
John Elam: それは非常に良い指摘だ。時として、メーカーとして品質上の問題が生じることがある。これは我々トヨタ文化の根幹にある—もしTPSを少しでも学んだことがあるなら、問題があれば生産ラインを停止することを知っているだろう。そして、もし問題が十分大きければ、何日も何週間も生産を停止し、その問題を解決してから車の生産を再開する。我々は意図的に不良車を作らないのだ。
その結果、非常に人気のあったある車種の生産を数ヶ月間中止したこともあった。だから、もし単に過去の平均値を使って将来を予測すれば、実際の需要が非常に蓄積されているにもかかわらず、予測は大幅に低くなってしまう。各ディーラーでは何百台ものこれらの車に対するバックログが存在する。だからこそ、予測が本来何であるべきか―需要を予測しているのか、あるいは過去の実績を予測しているのか―を見極める必要がある。
Joannes Vermorel: 主流のサプライチェーン理論の最大の誤りの一つは、再び時系列データに固執することである―まるでそれが一次元のベクトルであるかのように。しかし、ほとんどのビジネスでは、それだけでは現状を反映し得ないのだ。
一例を挙げれば、たとえば車の場合でも、需要は一次元的なものではない。車を待つことに問題がないか?例えば、メルセデスを欲しがるなら、問題ない—1年待てばメルセデスは車を販売している。つまり、状況によるということだ。しかし、需要を「1日あたりの車の台数」として平坦化してしまえば、その全ての次元を完全に見落としてしまうのだ。
そして、それらは必ずしも非常に複雑である必要はない。面白いのは、あなたが述べたように、極端な複雑性は求められていないということだ。例えば、以前あなたが言っていたように、シンプルなヒューリスティクスに基づいて、より多くのアクセサリーを提案するというロジック―優秀なディーラーの戦略をコピーする、それ自体もまた美しい。時には、適切な意思決定を導くためのエンジニアリングは、実際に高精度な予測を行うよりも桁違いにシンプルである場合がある。細かい未来の情報が不透明な中でも、良い決断には到達できるのだ。
John Elam: 他に頼るものがなければ、単純な在庫補充のロジックさえも非常に有用だ。
Conor Doherty: 改めて、意思決定に至るプロセスに関する議論を聞いていて、重要な点は—再び変革管理に戻るが—数学の専門家でない人たちは、どのようにしてこのプロセスに組み込まれていくのかということだ。なぜなら、もしあなたが数学の天才やウーンダーキンデとして入っても、異なる分野の専門知識を持つ人々がいる部屋で実行しなければならないからだ。正直に言って、どうやってそれを活用し、施策や最適化の取り組みを共同で作り上げるのか?他の人々の頭の中にある情報が必要なのに、それをあなたのプロセスにどう組み込むのかが問われる。
John Elam: 先ほどのコメントにも言ったが、PowerPointを持ち込んではいけない。なぜなら、それは自分が答えを知っていることを意味し、私はそうしたくないからだ。誰しも少しはエゴを持っていると思う。私はそれを共に築き上げたい。聞くところによると非常にシンプルに聞こえるが、本当にそれほど単純なのだ。そして、それがおそらく難しい点—つまり、非常にシンプルであるがゆえに、相手の問題は何か、彼らの言語は何か、彼らの知識は何かを理解し、彼らが抱える問題の所在に合わせて共に進むべき方向を定める必要があるということだ。
そして多くの場合、それは痛みを見出すことにかかっている―つまり、人々は自分たちの業務上で何が痛みであるかをよく知っている。しばしば、彼らが多くの時間を費やしている問題が実はそれほど解決の恩恵をもたらさない場合もある。しかし、彼らはしばしばこう理解している:「これが今日我々がやっていることであり、ここが問題だ」と。そして、その問題については十分に議論できる。多くの場合、その壊れている箇所は、自動化できるか、予測できるか、あるいは単純化できるものである。
だからこそ、彼らのいる場所で彼らに会い、その言語を学び取るのだ。先にも言ったが、彼らなしで何かを築くことはできない―共に作り上げ、彼らから要件を引き出し、必要ならば正しい答えへと導く。しかし、決して教え込んではいけない。つまり、人に何をすべきかを一方的に指示してはならない。これはどれほど強調してもしきれない―多くの人々は指示されることを嫌う。彼らは「アハ」の瞬間を愛する。だから、もしあなたが「あっちに答えがありそうだ、一緒に見に行こう」と導ければ、時には私自身が答えを知っていても、それを押し付ける必要はない。彼らにそっと示すのだ。
Adam Dejans Jr.: さらに単純で別の視点を挙げよう。しかし、私にとってこれまでの年月を通して、人間関係の構築こそが何よりも重要であると感じる。そして、いわゆる「パワーチャート」、つまり影響力のある人物のチャートを認識することも重要だ。組織図には、部下やマネージャー、エグゼクティブが記されるが、人々は権力や説得力がその階層上に必ず上ると考えがちだ。しかし、実際にはそうでないことが多いのだ。
しばしば、エグゼクティブの耳元でささやく誰かがいる。彼らが友人であったり何かの理由で、あなたが人脈を広げ、人間関係を構築し、ただ話を聞くことで、その後でより技術的な話を持ちかけると、相手はすでにある程度の信頼関係を構築しているため、耳を傾けてくれる。その点は非常に重要であり、多くの人、特に若手のエンジニアや科学者たちはこれを見落としがちだ。彼らは、そして多くの場合それは正しいが、客観的にはより良い答えを持っていると考えがちだ。しかし、それをそのまま実装することはできない。
そしてそれが、企業内で人々がいら立つ理由でもあります。客観的に見れば、もっと悪い解決策が存在する場合もあるのに、より良く売り込まれるからです。なぜなら、その人が単に話す力、販売力、または築いた人脈を通じて、より影響力を持っているからです。私たちの業務の一環としてキャリアコーチングも行っており、その中でこの点は非常に重要であると詳細に語られるセクションがあります。これはしばしば見落とされがちです。
Conor Doherty: あなたがトヨタ、日本本社との連携について話すのは知っています。そして、私自身が中国で5年間働いた経験から、その重要性を痛感しています。例えば「関係」という言葉を聞いたとき、私が思い浮かべたのは「グアンシー」で、これは大まかにネットワーキングや人間関係と訳せますが、中国ではそれがはるかに強い力を持つのです。上司や同僚と良好なグアンシーがなければ、何も進まない、いや正確には、非常に複雑になってしまうのです。たとえご指摘の通り、客観的に優れた、あるいは最も印象的なアイディアを持っていたとしても。
それは、いや、あなたが物事をまとめたやり方、部屋に入った時の態度、人々を愚かに感じさせた点、つまり彼らを巻き込まなかったという点に端を発しているのです。そこで質問ですが、「関係」とはそのような意味を含むのでしょうか?アメリカ人が日本企業で働く中で行う異文化間の仕事がどの程度影響しているのか、それとも一般的な意味で語っているのか、どちらでしょうか?
John Elam: そうですね、どちらでもあります。間違いなく両方です。しかし、日本のローコンテクストまたはハイコンテクスト文化においては、これが最も重要な要素であることには完全に同意します。実際、社内のウェブサイトにも取り上げられる「根回し」という日本語の言葉があります。直訳すると「土を準備する」です、つまり何かを植える前の土作りですが、文化的・社会的には「全員が同じ認識を持とう」という意味です。
そしてアダムが話していたように、非公式な権力図式であっても、実際この文化では特に、通常のヒエラルキーであっても、我々は皆、同じ認識を共有する必要があり、基本的には正式な決定が下る前に決まっているのです。つまり私の言いたいのは、正直に言って、あなたが言うようにそれが唯一の手段であり、私の経験上、この文化で物事を進めるにはそれが唯一の方法だということです。
私は、業務に中程度の影響を及ぼす可能性すらある全てのステークホルダーと一対一で関わり、私たちが何をしているのか、どのように彼らに利益をもたらすのか、彼らの環境に何が変わるのかを理解してもらわなくてはなりません。そして、何をするかを決定する会議においては、すでに決定はなされ、皆が答えを知っている状態になっています。正直なところ、その段階で何か問題があれば、前進はなく、再度戻ってさらに根回しをすることになるのです。ですので、これは非常に重要です。
しかしアメリカの文脈、たとえば私たちがコンサルティング業務を行う際でも、人間関係は最重要事項です—必ずしも全員を巻き込む必要はないものの、一定の臨界集団は不可欠です。もちろん、特定の人物には異なる影響力があり、それが権力図式全体を形成しています。しかし、前進するためには臨界集団が必要なのです。クールなアイディアや非常に優れた指標だけでは、組織の働き方を根本的に変えることはできません。
Conor Doherty: ジョアネス、すぐにあなたに投げかけたいのですが、私たちはフランス企業です—フランスはハイコンテクスト文化ですが—しかしフランス企業として私たちのクライアントの大半はフランス国外にあります。ですので、文化や物事の進め方について、あなたはどうお考えですか?
Joannes Vermorel: ええ、とても興味深いですね。私が観察したところ、特にアメリカの一部企業、特にテック企業は、非常にハードで対立的なマネジメントアプローチを採用しています。例えば、2002年のジェフ・ベゾスのメモをご存知でしょう。彼はチーム全体に向けて、「自部門のデータをAPIで公開する計画が2週間以内に提出されないマネージャーは、(既にそうでない場合)解雇する」と通知しました。そして結果的に、マネージャーの約15%を解雇しました。(正確な数字は覚えていませんが)
しかしそれは極端です。フランスでは考えられず、ほぼ不可能であり、非常に高コストになります。解雇は可能ですが、そのように行えば途方もないコストがかかるのです。しかし現実には、テック企業のほとんどはアメリカ発であり、Amazonはヨーロッパで誕生したのではなくアメリカで生まれました。そして、他のテック大手の経営手法を見ても、マイクロソフトは長年解雇はしなかったものの、様々な面で非常に過酷な手法を取って成功を収めたのです。
私の見解では、必要とされる根回しの量と過激さは、業界の変化の速さに多少依存します。業界が緩やかに変化するなら、日本式の着実で、皆を満足させつつ少しずつ改善を進める方法(つまり人的資産を失わない方法)が最良でしょう。
一方、ソフトウェアのように非常に速く進化する分野では、その方法を採用すると、雰囲気は良くても、結局は時代遅れとなり、あなたのビジネスが完全に他者に取って代わられる可能性が高いのです。ですから、その点には同意します。結局、答えは競合他社が何をしているか、どれほどの破壊的変化をもたらしているかに大きく依存すると思います。これが私の見解です—つまり、業界や時代によって異なるということです。
John Elam: それは本当に良い点ですね。なぜならソフトウェアの場合、例えばLokadを例に挙げると、もしLokadがある機能を導入し、それがあまり受け入れられなければ、すぐに機能を変更する。フィードバックも迅速に得られ、すぐに反復して新しいバージョンを出すことができるのです。
一方、プリウスを製造する場合、そのプリウスは20年間、いや私のこれまでの職業人生よりも長く稼働する可能性があるのです。だからこそ、初回で完璧に仕上げることが極めて重要になります。しかしあなたの言う通り、私たちはソフトウェアを構築しており、トヨタで働く中で直面する文化的変革という課題にも取り組んでいます。私たちはソフトウェアを作っており、アップデートが可能です。「何が問題か教えてください。反復します。来月には新しいものをお届けします。もっとフィードバックをください。」
そしてそのような考え方自体が挑戦ですが、会社は確実にそれを採用しています。少なくともソフトウェア面では、より柔軟で反復的になるようにシステムが回り始めているのが分かります。しかし、確かにそれは挑戦です。しかしあなたの言う通り、時と場所に合った正しい文化と哲学が存在すると思います。
Joannes Vermorel: もし大規模な変革が迫っているなら、過激さが勝つと私は考えます。しかし、ただ安定しているだけでは、無意味な混乱を生むだけです。そして、例えばこの絶対的な過激さの一例として、しかしながら良い決断であったのがTwitterの買収が挙げられます。彼らは最終的に従業員の90%を解雇し、その結果、製品はかつてないほど多くの機能を持つようになり、トラフィックも増加しました。これはもちろん、トヨタに問いかけるなら、「トヨタで働く従業員の90%を解雇することで、より多く、より良い車を作れると考えられるか?」という疑問になります。答えは、ありえません。
しかしソフトウェア業界では、このようなことが実際に起こります。そして、やはり全く異なる文化が存在するのです。興味深いのは、デジタルトランスフォーメーションの文脈で、これまで伝統的な方法で運営されていた企業に、急激で混沌とした業界の過激な、迅速な変化が浸透してきている点です。これは正当な理由から起こっているのです。
John Elam: これは間違いなくパラダイムシフトであり、技術者が伝統的な枠組みを持つ企業に参加する場合や、逆に伝統的な企業が大量のAIや機械学習の人材を採用する場合など、誰もが成長しているのを感じます。多少の摩擦はあるものの、良い経営は製造業的な環境に必要な調和と、変革に求められる進歩的・革新的な思考との間で適切なバランスを見出すものだと思います。
Adam Dejans Jr.: これはゆっくりとしたプロセスです。トヨタではゆっくりと、フォードでも同様でした—自動車業界ならではのことです。フォードでは、私が自律走行車グループで短期間働いた際、そのグループはまるでスタートアップのように扱われましたが、フォード・モーター・カンパニーの資金提供を受けていました。つまり、相当な資金があったのです。ええ、違いは明確に感じましたし、迅速に動く必要があったため、伝統的な自動車業界のヒエラルキーはあまり見受けられませんでした。しかし、やはり違う—ただ時間がかかるということです。
Conor Doherty: 例えば、私たちはこのやり方で30、40年も業務を続けてきたマルチビリオンドル企業です。一体、あなたは誰で、「ねえ、そんなことはやめろ」と言いに来るのですか?
John Elam: そうですね、「私たちより多くの車を作っている誰かを見せてくれ」と言われるようなものであって、そのときは大変な苦労が伴うでしょう。
Conor Doherty: 根本的にその通りです。たとえば、MITで数学の学位を手にして「これらすべてはくだらない」と主張するような人であっても、いや、あるいはあなたが語った洗練されたホワイトボードアプローチを取ったとしても、何十年にもわたる、並ぶものがなくかつ極めて高収益な成功にぶつかるのです。では、その結果、どれほどの抵抗が生じるでしょうか?「技術が好きではない」「技術に精通していない」といった抵抗もあれば、「いや、現状維持で十分だ」という抵抗もあります。
John Elam: 私は、デジタルトランスフォーメーションのために採用されるという運に恵まれたのです。彼らはその課題を把握した上で私を採用し、外部からの人材投入が必要であるという理由もありました。ですので、私が会社にいる理由は、現状の手法では我々が目指す場所に到達できないからであり、その意味では幸運です。しかし、私の直属の上司以外の各ステークホルダーが「ジョン、私はこの方法で長く成功してきた」という態度を取るわけではありません。
つまり、出力は実に様々な形を取り得るのです。前に述べたように、白手袋をはめたホワイトボードでのサービス、共創のアプローチなどがあります。時には、彼らのリーダーシップや経営陣に示す場合もあり、これの多くは権力図式に依存します。つまり、実際に意思決定レベル、例えばVPレベルで影響力を持つ人物を特定することが重要です。そして、その人物と繋がっている人を見つけることが肝要です。正直なところ、もしステークホルダーとの間で行き詰まりを感じたときは、彼らを迂回して、他の同盟者を通じて上層部に可能性を示す必要があるのです。単に「フランク対ボブ」とするのではなく、「フランクと仲間対、40年間この方法でやってきたボブ。こちらがあなた(エグゼクティブ夫妻)のKPIがどのように変わるかです」と導くのです。
しかし幸いなことに、私は「デジタルイノベーター」、正確にはデジタルトランスフォーメーションマネージャーとして採用されたため、電話が鳴ってジョン・エラムと名前を見れば、多くの人が「何かを変える話になる」と理解するのです。なぜなら、それがまさに私たちがこのデジタルトランスフォーメーションチームに採用された際の役割だからです。
だから、人々が連絡してくると、私たちがそこにいる理由を理解してくれるのです。正直言って、そのための魔法の解決策は存在しません。要は、人々と協力し、非常に多くの忍耐を持つことです。私が生きてきた中で、すでに長年この方法でやってきた人々、実際には私が36歳であることを考えれば、40年以上の経験を持つ上司すらいるのです。ですから、忍耐は非常に大きな力となります—ゆっくりとですが。
Conor Doherty: そして、あなたがこの話をする際、しばしばテック業界の例を出すのを知っています。それは、確かに大規模で確立された、数十年、あるいは50年や60年も続く企業よりも、はるかに機敏であるというのが普通です。そのような議論は、人々にどのように響くのでしょうか?
Joannes Vermorel: 実際のところ、ビジネスの歴史を振り返ると、非常に確立された企業であっても、それは安定の幻想に過ぎません。例えば、史上最も偉大な小売チェーンの一つであるA&Pは、ほとんど誰も覚えていませんが、20世紀の大部分にわたって世界最大の小売チェーンであり、アメリカに存在していました。しかし、今では店舗を全て失っています。
かつては無敵と思われた巨大企業も数多く消え去っています。私の見解では、市場は優れたフィルターであり、ソフトウェア業界—ちなみに「ソフトウェアが世界を食いつぶす」という傾向がありますが—ますます多くの業界が、善し悪しに関わらずソフトウェア業界のダイナミクスに従うようになるのは、ソフトウェアがあらゆる分野で占める割合が増しているからです。
例えば、SpaceXを見ると非常に興味深いことに、SpaceXは大部分がソフトウェア企業です。これはロケット企業ではなく、何よりもまずソフトウェア企業なのです。例えば、ロケットエンジンの大部分の改良は、優れたソフトウェアによる設計によるものであり、これがロケットの真の魔法の源泉なのです。ロケットのほとんどの魔法は、まるで超人的な操縦能力のように、発射台に触れる30秒前でも数百マイル毎時の速度でロケットを帰還させる能力にあります。
ちなみに、ロケットは着陸前に20Gの減速を行っています。もし人間であれば、その減速では命を落としてしまいます―あまりにも急激に減速しているのです。つまり、人間が20Gの減速を操縦することは不可能で、ここはソフトウェアだけが対処できる領域なのです。繰り返しますが、これは非常に困難な問題で、多くの壮大な失敗例もありますが、これが一例です。
そして例えば明日、自動車業界では、自律走行車が生産グレードに達すれば―現状が正確にどこにあるかは不明ですが―大部分がソフトウェアの戦い、プラットフォームやその他の要素となるでしょう。非常に興味深いのは、私がそのような業界を多く見ていることで、かつて「ソフトウェアが世界を食いつくす」と述べたVCの名前を忘れてしまいましたが、たぶんアンドリーセン・ホロウィッツだったと思います。
いずれにせよ、私はこのように考えており、多くの企業やそのサプライチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーションが、ソフトウェアによってもたらされる最大の変革の一端になると考えています。
Conor Doherty: アンドリーセンと言いましたか? マーク・アンドリーセンですか?
Joannes Vermorel: ああ、そうです、その通りです。正解です。
John Elam: そうですね、たとえばCircuit Cityが思い浮かびます。ヨーロッパで人気があったかは分かりませんが、アメリカでは非常に人気がありました―今はもうなく、破産しています。実は私、高校時代にあそこで清掃の仕事をしていたものです。
Joannes Vermorel: Radio Shackも同じです。Radio Shackもなくなりました。Nokia、Kodakも。
Conor Doherty: Kodakは以前にも話題に出た興味深い例ですね。私の記憶が正しければ、デジタルカメラを発明したのではなかったでしょうか? 記憶違いなら訂正してください。
Joannes Vermorel: 携帯型デジタルカメラ、そうです、それ以外には何もありませんでした。そして興味深いのは、Kodakは将来予測を立てていた点です―これもKodakの興味深い点の一つで、つまり予測をしていたのです。実際、1970年代初頭にある重役が、デジタルカメラの支配時期を2000年代初頭と見越しており、その予測はおよそ3年の誤差で正しかったのです。つまり、正確な予測があってもそれに基づいて行動しなければ、全くもって致命的ということです。
John Elam: 仮説があります。Kodakにはレンズ、カメラ、フィルム、サービスなど、さまざまな部門があったと思います―おそらくフィルムとサービスが会社の中で最大の割合を占めていたでしょう。ですから、その部門を担当する重役たちは意思決定に大きな影響力を持ち、自らの業務を守るための決定を下したのです。
Joannes Vermorel: それこそが全くその通りの理由でした。
John Elam: そうですね、それは―政治は常に付きまとうものですし、会社を助けるためのインセンティブを与えなければ、人々は自分の利益を優先するのです。つまり、インセンティブの仕組みについて、私がリーダーシップや他のテックリーダーと語るところですが、「与えたインセンティブ通りの結果が出る」ということです。人はコインで動くのです。私もコインで動いています。支払った分だけの成果が得られる。営業担当者―本当に彼らは純粋で、その成果がはっきりと見えます。正直、皆同じです。ですから、もし人々に自分の領域や王国を守るようなインセンティブを与えれば、必ずその通りになってしまいます。ですので、何にインセンティブを与えるかを注意深く見る必要があるのです。さもなければ、非常に愚かな大きな決定をしてしまいます。
Conor Doherty: Adam、John、もしもう一度戻って強調したい点や、何か補足があれば教えてください。もしくはこのままで大丈夫ですか?
John Elam: ええ、どう切り出すか考えていたところです。なぜなら、これは言語や人々とのコミュニケーションに関する話題で、我々の本にも取り上げた画像があるのですが、ここでは見ることはできません。しかし、後で皆さんにその画像をお渡しできればと思います。つまり、我々の本で「ワードホイール」と呼んでいる概念です。これはエモーションホイールから流用したものです。少しズームインすると、文字は読めないかもしれませんが、概念自体は非常にシンプルです。
外縁部には、最も技術的で具体的な単語があり、円の内側に移るにつれて、より一般的な単語になります。概念は本当にシンプルです。仲間―この通話に参加している多くの方々―は、ここ外縁部の言葉を使いますし、実を言うと、正直なところ、私自身も個人的にはもう少し中間層にいるかもしれません。私ならそう感じるのです。例えば、「貪欲な最良優先探索(greedy best-first search)」みたいな、ここで適切なものは何か―という感じです。
わたしはよくわかりません、パスファインディングアルゴリズムを学んだことがないので、もしそれがパスファインディングアルゴリズムだと言われれば、「少なくとも、どのカテゴリーにこの会話を分類すべきか、イメージできる」と思えます。しかし、重役―つまり最も中心に位置する重役や顧客―にとっては、単に「アルゴリズム」という最も基本的なものです。ただアルゴリズムを使っているだけです。パスファインディングという表現すら使わず、「パスファインディング?パスファインディングアルゴリズムとは何だ?」といった話題にはならないのです。
このように、適切な言葉遣いを選ぶことで、適切な聴衆と繋がることができます。具体的な情報を求める人々には具体的に、全く関心がない人々には―本当に関心がないので、情報を与えすぎないように―過剰な情報はただのノイズとなり、ノイズは本来のメッセージを損なうからです。
Conor Doherty: でも、ちょっと混乱しています。大きな言葉を使わなければ、どうやって人々はあなたが賢いと判断するのですか?学位を見せるようなものですか?ただメモをとっているだけですが。
John Elam: 大きな言葉を使って偉そうに見せるのは本当に難しいですね。重要なのは謙虚さです。そして、皆さんは私よりもはるかに多くのことを知っているという点も大きいです。私は、教えるより学ぶべきことの方が多いと常々感じています。
教えるということは、単に言葉や概念を述べるのではなく、相手と繋がることです。私の考えをあなたの頭に入れることであり、時には正確でない言葉―技術的には不適切な言葉―を使わざるを得ない場合さえあります。完璧な類推ではないにせよ、より理解を深めるためであれば、それで十分です。要点は、私ができることとできないことをより正確に理解してもらうことであり、完璧でない単純な説明が、聴衆によっては、完璧に詳細で高度にニュアンスを持たせた答えよりも効果的である場合が多いのです。
Joannes Vermorel: 少し反論的な視点もありますが、明らかに、聴衆の頭上を越えてしまう回答は良い回答ではないという点には同意します。しかし、LLMの時代にあっては、私は言葉が足りなくなることが非常に頻繁にあり、求めるべき質問をLLMに投げかけるためには、非常に豊富な語彙を身につけることが極めて重要だと気づきました。つまり、言葉に起こす―「私は何を質問しているのか?」ということです。そして、時には非常に具体的な単語が、どうしても思い出せなくなることがあるのです。
そして、これが非常に興味深い点であり、LLMの時代においては、キーワードをちらばらせることが聴衆にとって最良の手段になり得るのです。例えば、すべてのキーワードを持っていたとしても―そうですね、ここで一時間かけて全て説明するわけではありません―皆さんはLLMを使って自分で質問することができます。しかし、私は皆さんに、LLMに問いかけるべきキーワードのリストを提供しているわけです。するとLLMは、たとえ完全に賢明ではなくとも、特に概念やトリビアに関しては非常に広範な知識を持っており、例えば「根回し(nemawashi)」のような興味深いキーワードを与えれば、ChatGPTはおそらく3ページ分の概要を提供してくれるはずです。もし10ページ分が欲しいなら、それもできるでしょう。短い段落の概要であれば、同様に対応してくれます。
だからこそ、この語彙アプローチは以前とは少し異なると私は考えています。以前なら、学生に数多くの概念を並べ立てるのは時間の無駄だと言ったかもしれませんが、LLMの時代では―ああ、これは非常に興味深いのですが、彼らが持ち帰るべき一つの資料として、100の単語とその説明が記載された1ページが有益だと思います。
Adam Dejans Jr.: いや、非常に聴衆に依存すると思います。たとえ重役にこれらの単語を与えたとしても、実際は気にもしないし、調べに行くこともないでしょう。もし3分以内に要点が伝わらなければ、彼らは調べに行かず、LLMを使うこともないのです。つまり、聴衆を理解し、それに合わせることが重要なのです。何を意味するかは文脈次第です。
John Elam: 例えば、確率的最適化が何であるかを知らないシニアアナリストの場合―私が関わったほとんどのアナリストは非常に好奇心旺盛で、生涯学習者です。そのような人々には、大きな単語を羅列して自分で調べてもらいます。だから、あなたたち双方の意見に同意します。LLMのおかげで、今ではこれまで自分では調べなかった多くの事柄を学べるようになりました。特に、LLMには歴史があり、私が知っていることを把握しているので、「あの他のプロジェクトでやっていることと似ている」といった具合に答えてくれるのです。これが非常に助けになっています。
しかし、Adamの言う通り、私が関わった多くの重役は、率直に言って、ある概念をさらに深く掘り下げるような自然な好奇心を持っていません。だからこそ、ポイントはしっかりと伝わる必要があるのです。
Adam Dejans Jr.: 中間管理職でさえ―ええ、多くの中間管理職はこのようなことに関心を示しません。
Conor Doherty: 私はあなたのやり方が非常に好きです―まあ、皆さんも説明している通りですが、私自身は修辞学やテクニカルライティングを教えているので、基本的にあらゆるコミュニケーションにおいて、私が適用している視点は―そして皆さんに送るメッセージの中にも表れているように―聴衆と目的です。つまり、誰に話すのか、彼らはすでに何を知っているのか、何を知る必要があるのか、既存のスキルは何か、という点です。そして目的とは、正確に何を伝えたいのか、彼らから何を得たいのかということです。メール、テキスト、ブリーフィング、パワーポイント、スピーチ、ビデオ―すべてにおいて、聴衆と目的は不可欠です。誰が見ているのか、何を伝えたいのか、または何を得たいのか、なぜそれを行っているのか、という点を理解することが必要です。そして、再びあなたの言う通り、Adam、聴衆を理解することが鍵です。つまり、聴衆が現在の状況を理解するための既存の知識を持っているか、時間や意欲があるかといった制約が存在します。これらはすべて変動する優先事項であり、異なる条件です。例えば、彼らが疲れているのか、午後6時のために脳内のグリコーゲンが不足しているのか―という状況です。
本当に、時差のため午後6時になっているのです。あなたはその日を始めたばかりでフレッシュで、コーヒーを一杯飲んだところ―彼らは疲れ果てています。つまり、それが文脈です。さて、最終質問に移ります。もし修辞学についてもっと学びたいのであれば、私はアリストテレスをお勧めします。しかし、もし確率的予測やサプライチェーンについて知りたいのであれば、今回のインタビューで実施した投票で、「皆さん―コナー、聴衆またはパネルに対して、サプライチェーン最適化、確率的予測、または単なるアドバイスに関する何かお勧めがあれば尋ねてください」と非常にシンプルな質問が寄せられました。では、最後の質問ですが、順番を逆にして:Joannes、もっと学びたい人向けの書籍の推薦やアドバイスはありますか?
Joannes Vermorel: つまり、私がYouTubeで制作した講義シリーズです―正直なところ、何時間も視聴できる方なら、内容も悪くないはずですが、これは100時間に及ぶ旅ですので、時間とコミットメントが必要です。
Conor Doherty: しかし、トランスクリプトを要約できるLLMもあります。はい、完全なトランスクリプトはウェブサイトにもあります―もしLLMがあれば、それを1ページに凝縮することもできるでしょう。ええ、それでは、John。
Adam Dejans Jr.: どうして皆のためにそれをやって、私たちに噛み砕いて説明してくれないのですか。
John Elam: まず―私が推薦する一冊は、もちろん私、プロダクト担当者からの推薦ですが、『The Lean Startup』、エリック・リース著です。決して技術書ではありません―実際、この聴衆にはあまり耳にしないかもしれませんが―この本はすべてプロダクトと問題解決について書かれています。エリック・リースは非常に良い本を書いており、一般的な意味で、どのようにアイデアをテストするかという非常に良い事例がいくつか挙げられています。
さらに、彼はさまざまな政府機関がいかにして効率化し、市民により多くの価値を提供できるようになったかについても語っています。技術を一切使わず(ゼロテックで)スタートした多くのスタートアップの例を示し、「これは本当に解決すべき問題なのか、人々はその解決に対してお金を払うのか?」という疑問を投げかけています。彼らは実際に手作業で物事を進め、手動でメールを送りながら、この問題を解決する価値があるのかどうかを検証しているのです。なぜなら、時には存在する問題を解決するために多額の費用をかけても、誰もその問題を解消するためにお金を払おうとはしないからです。だからこそ、私が薦める一冊は『The Lean Startup』、エリック・リース著なのです。
Adam Dejans Jr.: ええ、もし技術書をお探しなら、たくさん見つかると思います。私がかつてのコンサルティング時代に読んだ『Just Listen』という、マーク・グールストン著の本に戻ります。この本は、人々を防御的な態度から共感を共有し、説得へと導く方法について書かれており、技術的な側面よりも重要だと感じます。技術的な概念はどこかに必ず見つかるものです。そして、もちろん、我々自身の本―『You got the data job, now what?』もあります。
“You Got the Data Job, Now What?”――これはジョンと私が共著した本です。この本は、私たちが非常に賢い多くの同僚が、自分のアイデアをうまく提示できなかったり、適切な人脈や基盤を築いていなかったために、そのアイデアが見過ごされがちであるという現実に気づいたことから生まれました。ジョンに詳しく話してもらいましょう。
John Elam: ええ、この本をまとめるのはとても楽しかったです。なぜなら、これは基本的に私自身がキャリアを通じて感じたすべての問題と、アダムがキャリアを通して感じた多くの問題の集大成だからです。つまり、良いキャリアを築き、職場で影響力を発揮するための基本的な要素について解説しているのです。そして、「職場での影響力」と言っても、学術の分野でも同じです――もし、あなたがとてもすごい新しいアルゴリズムを作り、それが多くのジャーナルでレビューされたとしても、誰にも使われなければ意味がありません。少なくとも、あなたの研究が、たとえあなたが亡くなった後でも、使われることを望むものです。
そして、本書はコミュニケーションを最初の章として始まります。コミュニケーションにはたくさんの小さな要素があり、私が若いエンジニアだった頃、「これが正しい方法だ――客観的に正しい、なぜならそうだから」と、ただ示そうとしたのです。しかし、私たちは人間です。感情豊かで、物語を愛し、物語に共感する社会的な生き物なのだと学びました。
そして、本書には私たちが共有した単語ホイールに関する多くの情報や、さまざまなストーリーテリング技法、そして実際にコナーが話していた、プレゼンテーション時に自問すべき5つの質問、「なぜここにいるのか、なぜ聴衆はここにいるのか、彼らはどんな状況にあるのか、何を本当に伝えたいのか、そしてその後の行動喚起は何か」というフレームワークが含まれています。
もしそれを実行しなければ、ただ話しているだけで、あなたの主張がなんとか伝わるかもしれませんが、「これが伝えたいことで、彼らが今どこにいるか」という形で示すことができれば、彼らを正しい方向へ導くことができます。また、初めてのデータプロジェクトをどのように始めるか、具体的にどういう形になるのか、といった、プロジェクトに参加したことはあっても初めから終わりまで自分で運営したことがない人々向けの情報も含まれています。
そして、本書で私が触れたい最後の、しかししばしば見過ごされがちな点の一つは、リーダーシップに関するセクションです――公式なリーダーシップ、非公式なリーダーシップについて語っていますが、若いエンジニアの頃に早く学んでおけばよかったと痛感する主な点の一つが、ビジネスケースの作成方法でした。もしそれを知っていたなら、もっと多くのプロジェクトが資金提供され、私が働いた企業にとってもより大きな貢献ができたでしょう。
そして、ビジネスケースから皆さんに持ち帰ってほしい最も重要な点は、その驚くほどシンプルな点です。私が見たビジネスケースで、10項目以上あるものは一度もありませんでした。いつも、「これが今日やっていること、これが毎月のコスト、これが明日やりたいこと、これが固定費、これが変動費、これが差額」といった感じで、人々は「どこにサインすればいいの?」と言います。本当にシンプルです。「ナプキン一枚で」という表現を強調してもしきれません。お金に関するビジネスの決定が、ナプキン一枚でなされなかったことはないと思います。
私たちは、その時点で持っている情報を基に、できる限り最良の判断を下そうとしているだけです。ですから、皆さんが本書から何らかの価値を見出してくれることを願っています――また、私たちの成功談や失敗談といった楽しいエピソードも含まれているので、ぜひ役立てていただければと思います。
Conor Doherty: 最後に、本書はAmazonで入手可能であることを申し添えておきます。そう、君たちが恥ずかしくて言えなかったので、僕が代わりに告げました。でも、とにかく、皆さんありがとう。これ以上質問はありません。アダム、ジョン、本当に長時間お付き合いいただき、感謝しています。
John Elam: とても楽しかったです。お招きいただき、ありがとうございました。
Conor Doherty: 他の皆さんにも感謝します――さあ、仕事に戻りましょう。