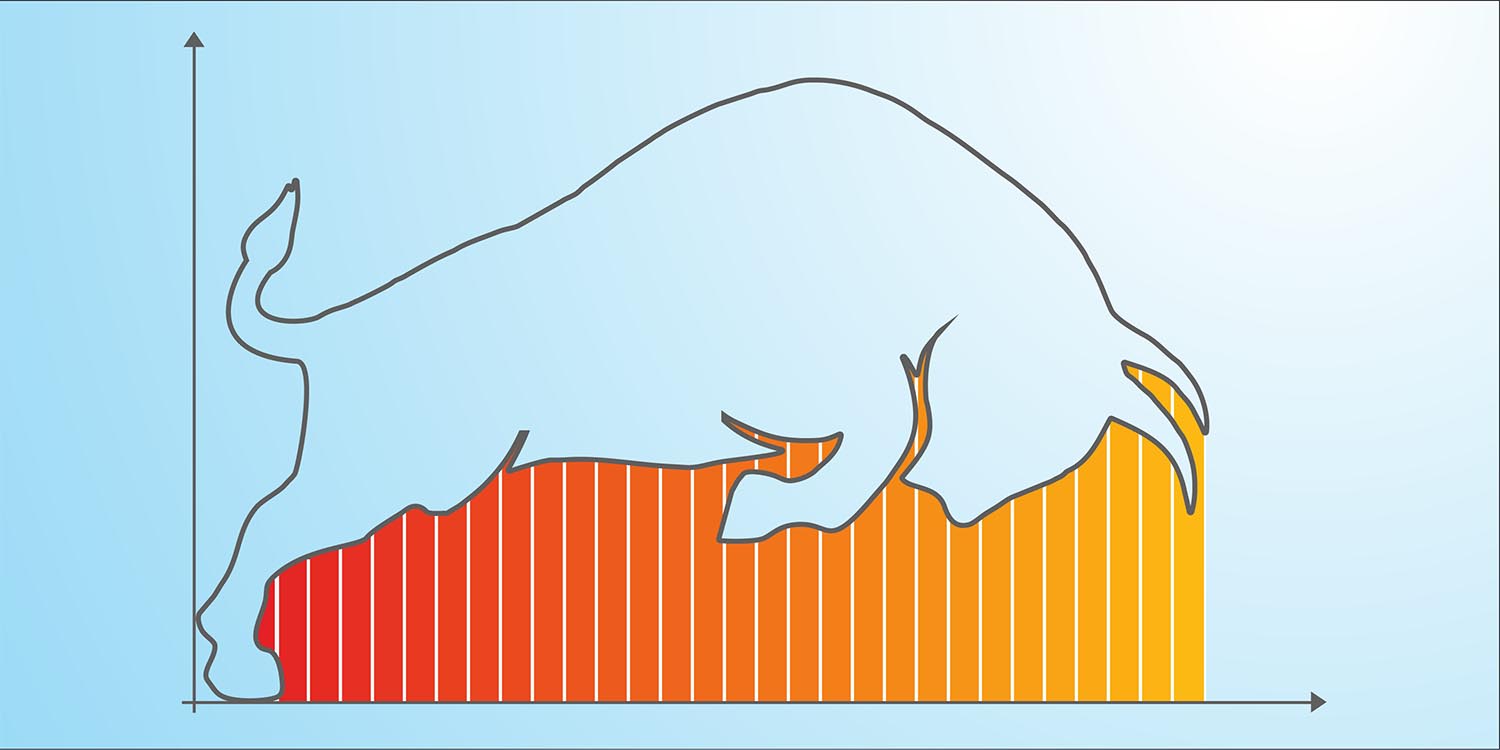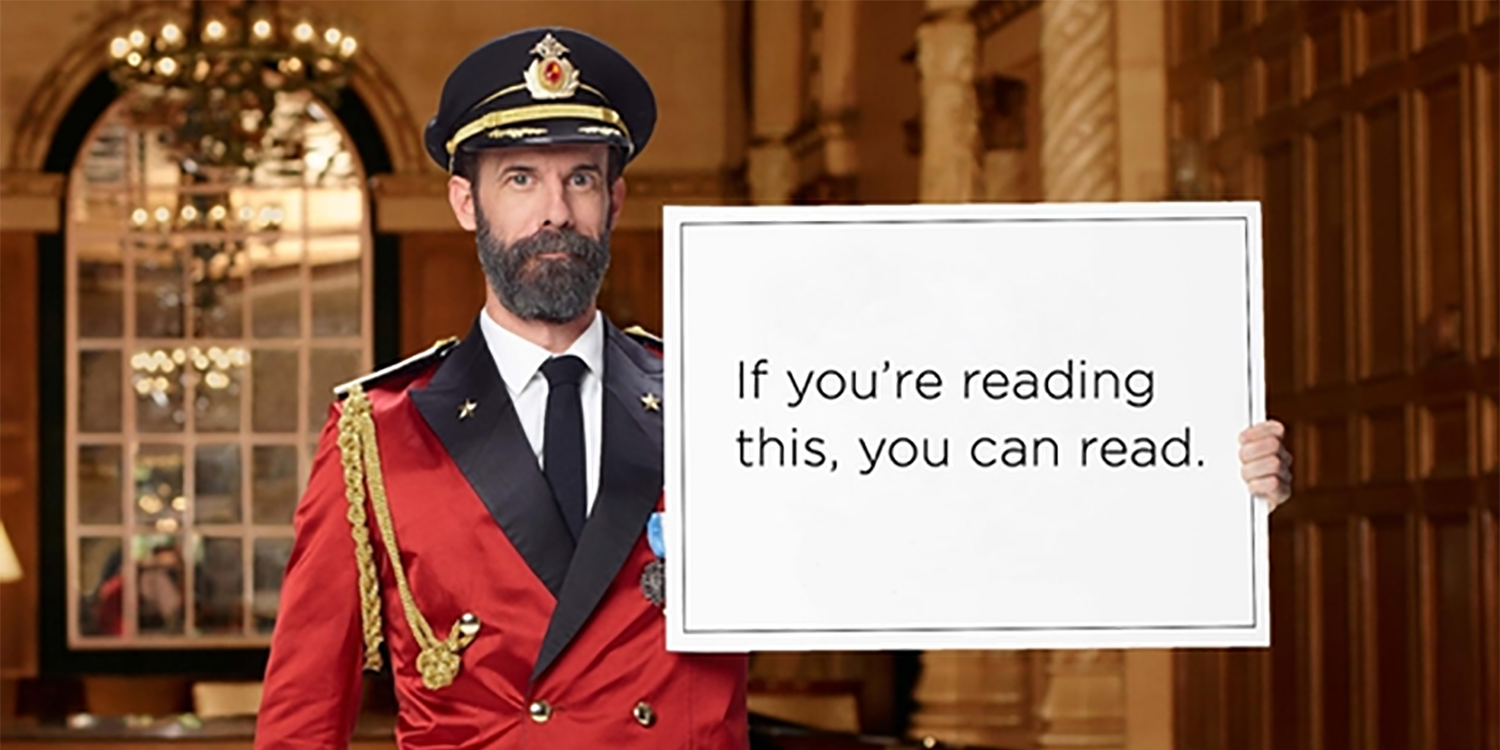サプライチェーン用語の豆知識
用語が生まれる過程は、いずれも偶然の産物に過ぎない。サプライチェーンも例外ではなく、その用語のかなりの部分は不十分である。混乱を招く用語は、新規参入者にも熟練の実務者にも悪影響を及ぼす。新規参入者は、予期せぬ複雑性に通常以上に苦しむことになり、実務者は自分たちの分野の前提条件が見かけほど堅固でないことに気づいていないかもしれない。

サプライチェーンにおける用語の中で最も問題のあるものを概観し、適切な代替案を提案しよう。たとえその代替案がコミュニティで採用される可能性が低くとも、見落とされがちなニュアンスに光を当てるはずだ。経験則として、良い用語とはできるだけ中立的かつ事実に基づいたものでなければならず、肯定的または「クールな」修飾語を含むのは警戒すべきサインである。
ABC分析 は 移動平均セグメンテーション と呼ぶべきだった。用語として、「ABC」という言葉は何も示さず、「analysis(分析)」は非常に曖昧である。「移動平均セグメンテーション」という表現はより具体的で、この手法に内在する欠点を明確にする。実際、_移動平均_は時間の経過とともに不安定さを生み出すだけでなく、循環性といった主要なパターンの反映にも失敗する。また、セグメンテーションは 粗野な メカニズムであり、その設計上、SKU レベルでの細やかな対応は不可能である。
APS(先進的計画・スケジューリング)は プランニングマネジメント と呼ぶべきだった。まず、これらのソフトウェア製品には「先進的」と呼べる要素が全くない。この用語は1990年代に、数多くの ソフトウェアベンダー を盛り上げるためにマーケットアナリストによって造られたものである。APSの傘下にある多くの製品は、2020年代の基準ではもはや「先進的」とは言えない。次に、プランニングマネジメントは大量の手動データ入力によるプロセスを重視しており、統計機能はソフトウェアの極わずかな部分に過ぎず、主にサプライおよび 需要プランナー といったエンドユーザー向けに設計され、彼らが計画を手動で管理している。
BI(ビジネスインテリジェンス)は キューブレポーティング と呼ぶべきだった。まず、この技術は「人工知能」や「諜報機関」といった意味でのインテリジェンスとは無縁であるため、「インテリジェンス」という用語は不適切である。次に、この技術に本質的に「ビジネス」固有の要素はなく、たとえば郵便番号ごとの過去の気温を表示するのは、キューブレポートの有効な使用例である。キューブレポーティングは、OLAP(オンライン分析処理)とも呼ばれるキューブ型データストア上に重ねられたユーザーインターフェースであり、キューブはスライス&ダイス操作を提供する。なお、「キューブ」という用語が使われているが、次元数が必ずしも3である必要はなく、高次元になると組み合わせ爆発のため、実際には一桁に収まる。
ERP(エンタープライズリソースプランニング)は ERM、すなわちエンタープライズリソースマネジメントと呼ぶべきだった。ERMの主な目的は、その名が示す通り、企業の資産を追跡することであり、これらの製品はプランニングとはほとんど関係がない。リレーショナルデータベースに大きく依存するERMの基本設計は予測能力とは相容れない。1990年代にマーケットアナリストたちが、競合他社との差別化を図るために「ERP」という用語を押し出したが、「プランニング」部分には実質が伴っていなかった。ソフトウェア的には、トランザクション領域と予測領域はかつてないほど明確に区別される。
MRP(資材所要量計画)は MRM(製造要件管理) と呼ぶべきだった。その理由は基本的に、ERPとERMの議論で述べたものと類似している。プランニングはほとんど存在せず、存在するとしても設計は 手動プロセス に大きく依存している。また、requirements という用語は時代遅れであり、現代の製造管理においてごく一部に過ぎない BOM(部品表)の管理を主に指すため、特にこの用語を強調する理由はほとんどない。
Eaches (EA) という単位は、より適切に 明らかな単位 (OU) と呼ぶべきだった。Eaches は、在庫管理において単位が自明であると期待される場合、通常はパッケージ商品のような状況で用いられる。しかし、「eaches」という用語では本来の意図が失われ、文法的にも奇妙であり、単数形の「1 each」は混乱を招くため、実際には避けられている。
EDI(電子データ交換)は1970年代に起源を持ち、主に購入注文を仕入先に送信し、注文プロセスから事務的介入を排除するソフトウェアを指す。残念ながら、インターネットの普及に伴い、ウェブサーフィンでさえ技術的にはEDIプロセスに該当するようになった。各自のITシステムの統合をほのめかす 統合された仕入先(逆に統合された顧客)という概念の方が、この状況を適切に表現できるだろう。
EOQ は フラットバルクオーダー と呼ばれるべきだった。実際、この用語の背後には、広範な意図を示しているようでありながらも単純な数式が潜んでいる。その数式は、将来の需要が一定(季節性なし)、リードタイムが一定(変動なし)、発注コストが一定(価格割引なし)、そして在庫コストが一定(有効期限なし)であることを前提としている。フラットバルクオーダー という表現は、その実際の単純な性質を適切に伝えている。
「Order(注文)」は良い言葉だが、単独では非常に曖昧である。顧客注文、仕入先注文、生産注文、在庫管理の注文、スクラップ注文などが存在する。この表現の意味を明確にするためには修飾語が必要であり、「レベル」という用語も同様に、修飾語なしでは用いるべきではない。
安全在庫 は ガウスバッファー と呼ばれるべきだった。実際、この手法には安全な要素と呼べるものはなく、将来の需要とリードタイムの両方が正規分布(ガウス分布)に従うことを前提としているが、サプライチェーンの領域では関心のある分布は正規分布ではないため、決して成立しない。バッファー という用語は、在庫に関する意図を明確にし、特定の美徳を示唆することなくその本質を伝えている。
季節性 は良い用語だが、通常、サプライチェーンの視点からは 周期性 という用語の方が適切である。実際、需要パターンの分析を年間の周期性、すなわち季節性に限定するのは意味が薄い。曜日や月日という他の明白な周期性も常に考慮されるべきである。したがって、サプライチェーンの責任者は季節性分析よりも、周期性分析を求めることが多い。
サービスレベル は サービスレート と呼ばれるべきだった。これは フィルレート とより一貫性のある表現である。「レベル」という用語は在庫水準のように数量を示唆するが、サービスレベルはパーセンテージである。これはこのリストの中でも比較的小さな問題かもしれないが、サービスレート と フィルレート という二面性をより直接的に伝えられるなら尚更良い。
サプライチェーンの新規参入者でさえ、より良い用語によって恩恵を受けるだろう。
DDMRP(需要駆動型資材要求計画)は スパース・プライオリティード・バッファリング と呼ぶべきだった。実際、この手法はフローとは対照的に「真の」需要を切り離すための具体的手段を提供していない。検閲、カニバリゼーション、または代替は、この枠組み内では数値的に存在しない。同様に、多くのプランニング手法(レンジプランニング、フェーズイン、フェーズアウト、プロモーション など)も、この数値枠組みには含まれていない。キーワード「sparse(まばらな)」は、「デカップリングポイント」の導入に関する意図を的確に表している。
デカップリングポイントは マネージドSKU と呼ぶべきだった。DDMRPは、SKUをデカップリングポイントとその他に分けるグラフ彩色方式を提案している。これらの「ポイント」をSKUと呼ぶ方が明確であり、さらに、これらのSKUだけが需要・供給プランナーにより実際に検査される対象であるため、「マネージドSKU」という表現は適切であり、他のSKUがプランナーの観点から「非管理」とされることを明確にする。
特定の状況下では、劇的な簡略化が実現できる。
人工知能、自律システム、ブロックチェーン、コグニティブシステム、需要センシング、需要シェイピング、デジタルブレイン、ナレッジグラフ、最適アルゴリズムは、本質的にはすべて マジック という言葉に置き換えることができる。これらのバズワードの一部はサプライチェーンの枠外では実際のエンジニアリングが存在するものの、サプライチェーン向けエンタープライズソフトウェアの文脈では、純粋な意味でのヴェイパーウェアである。
最後に、たとえ時折批判を受けたとしても、一部の用語は依然として適切である。
バリューチェーン は、時折 サプライチェーン の代替として提案されることがある。この置き換えは、19世紀初頭の経済学者ジャン・バティスト・セイに因むセイの法則の理解不足を反映している。この法則は 供給が需要の源である と要約できる。供給が第一、需要が第二、取引が成立したときに価値が生じ、チェーンが全体を束ねる。バリューチェーンは主に、見込み客にROIを売り込もうとするコンサルタントによって推奨されるが、「value」という用語は「supply」と比べ、特定性に欠け、かつ肯定的なバイアスがかかっている。